「知らぬが仏、言わぬが花」
カーテンの引かれた窓ガラスを叩く微かな音が聞こえてくる。また雨が降り出したようだ。俺は小さく息を呑んだ。
落ち着いていた心拍数がゆっくりと、確実に上昇していくのを覚える。内側で煮え滾った熱は行き場を失い、皮膚を生温く湿らせた。そのうち、それは首筋を伝ってTシャツの中へ滴り落ちた。
浅い呼吸を繰り返しながら、俺は必死でキーボードを打ち続けた。そうでもしていないと、迫り来る不安と恐怖に飲み込まれてしまいそうだったからだ。きっと一度でも手を止めてしまったら、俺は椅子の上で固まったまま、何もできなくなってしまうだろう。まだ死にたくない。ああ、死にたくない。こんな六畳一間の自宅で孤独死だなんて。
さっきから何を言っているんだ。この匿名掲示板をもし見ている人がいたら、そう思っているに違いない。自分でも頭がおかしくなったのではないかと思う。けれど、これはリアルに起こったことなのだ。全てを信じてくれとは言わない。けれど、もしこの書き込みが途絶えたら、警察に連絡して欲しい。俺の名前は大澤賀正。住所は……だ。見知らぬ友よ、どうか頼む。
では、そろそろ事の顛末をお話ししよう。長くなりそうだから、結論から先に言う。心して聞いて欲しい。
この部屋には、霊がいる。
いきなり何を言っているんだ。これを読んでいる君はそう思っていることだろう。もしかしたら、このスレッドすら閉じようとしているかもしれない。お願いだから、最後まで聞いてくれ。さっきも言った通り、これは信じがたい事実なのだ。
それは、遡ること数時間前。俺は昼寝をしていた。平日の昼間に家にいるなんてニートかと思われそうだが、違う。こう見えて、俺はR社で営業をやっている。なので、本来であれば週五ないしは週六で会社に足を運んでいるところだ。しかし、このようなご時世。例外なく俺も自宅勤務や時差出勤を強いられ、今では週に二回ほどしか会社に行かなくなった。
この働き方は、俺みたいな外勤営業マンにとってはなかなかの痛手だ。全く数字が取れない。嫌というほどカラフルに彩られていたはずのグーグルカレンダーは真っさらになった。社会人になってこれほど存在意義の不必要性を感じたことはない。けれど、人間というのは意志の弱い生き物だ。おまけに順応力も高い。三日も経つと、俺は必要最低限のタスクしかやらず、上司という監視の目がないのを良いことに家でぐうたらし始めた。
今日は昼食を取り終えてから、ベッドに寝転がった。頭側を両引きの窓にぴったりとくっつけた配置のため、仰向けになると空を臨むことができる。白い雲が漂う初夏の陽気は、開け放たれた窓から心地よい風を運んできていた。腹が満たされ、身体も温かくなっていた俺はそのまま目を閉じた。
どんな夢を見ていたのか覚えていない。それほど悪いものではなかったように思う。しかし、寝覚めは最悪だった。べったりとした蒸し暑さに身を包まれたまま、俺は薄目を開けた。頭上の天気は一転。空は分厚い灰色の雲に覆われ、今にも一雨来そうだった。
ぼんやりとした頭で俺は枕もとに置いていたスマートフォンに目をやった。かなり長い間眠っていたような気がするが、実際には十数分程度しか経っていなかった。まだ大丈夫だ。俺は寝た体制のまま窓に手を伸ばした。外の音が徐々に小さくなっていく。完全に閉め切った後、俺は再び眠りの海へ身を投じた。
二度寝から目覚めると、これまた最悪な出来事が待っていた。スマートフォンを見た俺は目を疑った。驚いたことに、一時間どころか二時間以上も寝てしまっていた。急ぎの電話やメールは来ていなかったものの、あと数分後にはオンライン会議が始まる。やばい。俺は慌てて跳ね起きた。
結局、その日の仕事が終わったのは二十一時前だった。俺はパソコンを閉じると、夕食を買いに近くのスーパーへ向かった。この生活になってから、外食よりスーパーに行くことが格段に増えた。むしろ、最近は家とスーパーの往復しかしていないように思う。
スーパーから帰って、ドアを開ける。すると、玄関を上がってすぐ右手の六畳間の扉が勝手に閉まった。風圧と分かっていても、ビビらずにはいられない。お察しの通り、俺はホラーが大の苦手だ。去年、彼女の千夏と遊園地へ行った時、お化け屋敷に入りたいと提案されたのを思い出す。彼女の手前、つい格好つけてしまったものの、いざ入ると恐怖でまともに声が出なかった。彼女でなければ、きっと相手を置いて逆走していたことだろう。
部屋に入り、作業机の上にビニール袋を置いた。適当に片づけ、夕食を取るスペースを作る。ふとカーテンを閉め忘れていたことに気づいて窓に近づいた。二度寝をしている時にかなりの量の雨が降ったのだろう。窓ガラスにはいくつもの水滴痕がついて、下の方が湿気で曇っていた。
俺はそこであり得ないものを目にしてしまった。心臓が跳ね上がったことは言うまでもない。咄嗟にカーテンを引いた。確認する勇気はなかった。もう一度言う。俺は見てしまった。窓ガラスにいくつかの手形がついているのを。
ここは六階建ての四階だ。角部屋でもない。だから、あり得ないのだ。スパイダーマンでもない限り。
俺は千夏に『今日うちに来ない?』と急いで連絡をした。こんなご時世で無神経なことは分かっている。しかし、こっちもこっちで緊急事態宣言なのだ。それに、彼女は身内みたいなものだ。ギリセーフだろう。そういうことにしていただきたい。
千夏は『明日早いから無理』とあっさり断ってきた。なんと薄情な女である。とはいえ、総合病院で看護師として日夜働いている彼女に文句は言えない。せめて会話だけでもと思い、いつものようにメッセージでやり取りをすることにした。何も知らない彼女は俺の異常な返信の早さに戸惑っているようだった。けれど、お化け屋敷であれだけ虚勢を張ってしまったのだ。正直には言いづらい。「今日は話したい気分で」と何とか誤魔化し、他愛ないラリーを続けた。
『それでね、ユウト君、EDになっちゃったらしいのよ』
千夏の言葉に思わず「えっ」と声を漏らした。ユウトは俺と千夏の大学時代の同期だ。
『なんで? それにその話、どこで聞いたの?』
『理沙が言っていたのよ。何でも突発的にらしいわ。最初はお互いに仕事のストレスや疲れかなと思っていたみたいなんだけど、他に不調はないらしいのよ』
『じゃあ、原因は分からないってこと?』
『うん。二人で病院にも行ったみたいなんだけど、検査結果は特に異常ナシみたい。それで理沙、将来は子供を産みたいと思っているから、このまま付き合い続けるか悩んでいるみたい』
『そうなんだ』
スマートフォンの画面の前で俺は腕組みをした。
『治療して快方に向かうことを祈るしかないね』
『でもさ、私はユウト君には悪いけど、自業自得なんじゃないかなともちょっと思うんだよね』
『自業自得?』
『うん。だって、ユウト君呪われているみたいだから』
背筋が凍りついた。忘れかけていたことが脳裏をかすめる。や、やめろよ、と俺は引きつった笑みを浮かべた。
『冗談だろ?』
『冗談じゃないよ。だってユウト君、そうなる半年くらい前まで浮気していたんだもん』
『浮気?』
俺は眉を顰めた。千夏と理沙ほどではないが、俺とユウトだってそれほど遠くない間柄だ。けれど、そのような話は一度も聞いたことがない。
『何でも、会社の部下の子とだったらしいわ。まあ、正確には彼にその気はなかったみたいなんだけど。若い子に鼻の下伸ばしてしょっちゅう二人で飲みに行っていたユウト君もユウト君だわ』
突き放すようなはっきりとした言い方が千夏らしい。彼女が続ける。
『それで、その気になっちゃった部下の子がユウト君に彼女と別れて付き合って欲しいってなって。そこでユウト君、やっと気づいたみたいなのよね。慌ててプライベートで会うのはもうやめようって言って断ったらしいの。そんなの、勝算しかないと思っていた彼女からしたら大誤算じゃない? 案の定、逆上よ。実際、自宅への無言電話とか嫌がらせが酷かったみたい。だから理沙がおかしいと思って、白状させたってわけ』
『……その後、どうなったの?』
『理沙が警察に通報したみたいよ。それで嫌がらせは収まったみたい。部下の子はちょうど異動になったからそれ以来顔を合わせていないらしいわ。でも』
『でも?』
『ユウト君、逆上された時に言われたらしいのよ。呪ってやるって。それから時折、視線を感じるらしいわ。全く。女の怨念って怖いわね』
俺は唾を飲みこんだ。学生時代の思い出がふと頭を過ぎる。千夏と付き合ってからは彼女の圧が怖くてなくなったものの、それまでは何人かの女性と遊んでいた。
どれも自然消滅したものだから、すっかり終わったものだと思い込んでいた。けれど。もし、その中にあの頃のことを根に持っている人がいたとしたら……。
千夏がもう寝ると言い、メッセージは途絶えた。会話する人がいなくなったことで先ほど以上に孤独さが増した。上の住人の足音や部屋の軋みと言ったイレギュラーな環境音に肩がびくりとなる。いても経ってもいられなくなった俺は、一度閉じたパソコンを起動させていた。そして、今に至る。
長々と語ってしまったが、俺が置かれている状況をお分かりいただけただろうか。そして、ここで一つこれを読んでいる君に伝えなければならないことがある。それは、ここまで一心不乱にキーボードを打ち続けた疲労と話すことがなくなった放心から、どうしようもなく眠気が襲ってきているということだ。あんなに昼寝をしたというのに。やはり人間、本能には抗えないということだろうか。いや、ここで寝てしまってはいけない。朝を迎えるまで頑張るんだ。そうしないと、殺されてしまう。
……果たして、本当にそうなのだろうか。カーテンを閉めているうちは相手も襲ってこないんじゃないだろうか。何となく、ギリセーフな気がする。それにこの眠気だ。殺されたら殺されたで諦めるしかない。は? 諦めるって、何をだ。こんなところで寝てはいけない。こんなとこrでyぇfりhんfrm……。
◆
翌朝。彼はベッドの上で目が覚めた。どうやら、睡魔に負けて眠ってしまったらしい。カーテンの隙間からは外の光が漏れている。彼は息を吸った。そして、一気にカーテンを開け放した。
驚くべきことに、手形はまだ残っていた。おそらく昨日と全く同じ場所にだ。こういう場合、普通は増えたり消えたり何か変化が起こっているものなのではないだろうか。彼はまじまじと見つめた。
ごつごつとした指と幅の広い手のひら。大きさからして女性のものとは思えない。それに何だか見覚えがある。そう思った途端、彼ははっとした。
手形を凝視したまま、恐る恐る自分の手のひらを合わせてみる。すると、それは寸分の違いもなく、ぴったりと重なった。そこで彼は事の顛末をようやく理解した。昨日窓を閉めた時、寝ぼけていたものだから窓ガラスをべたべたと触ってしまったのだと。
「なあんだ」
彼は微笑んだ。全身の力が抜けていくのを感じた。帰ってきたらしっかりと窓の掃除をしよう。彼はそう心に決めた。そして、とりあえずTシャツの裾で手形の部分を拭ってから、ベッドを降りた。今日は久しぶりの出勤だった。
恐怖の謎が解けた途端、昨日の出来事は彼にとって些末な記憶となってしまった。朝の支度を終えた彼は慌ただしく自宅を出て行った。そう。彼は気づいていなかった。この世で最も恐ろしいこと、それは、インターネットという得体のしれない情報の海へ名前や住所、勤務先と言った個人情報を自ら流出させてしまったということに……。
(完)

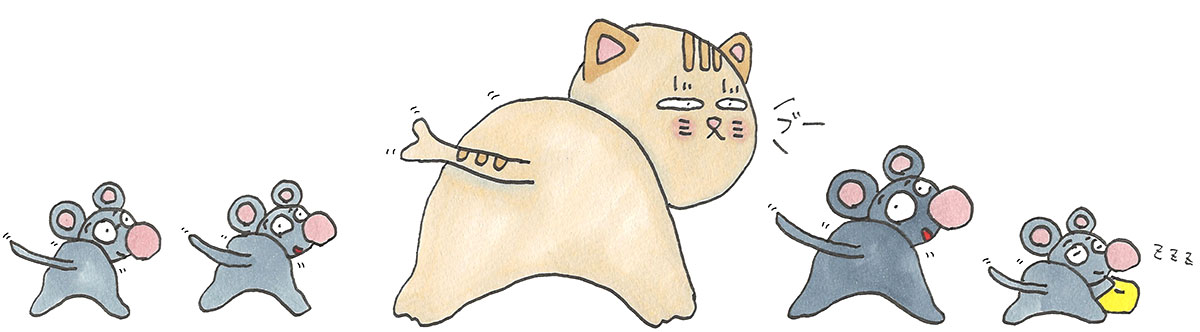







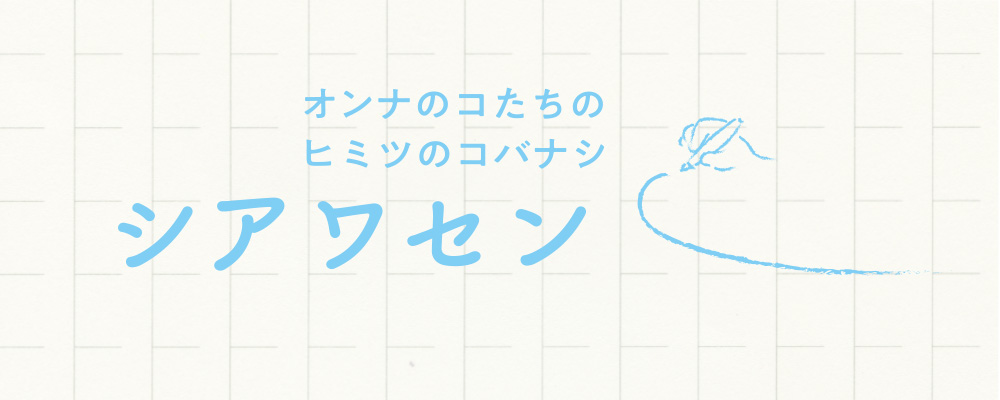

COMMENTS