「初夏の尋ね人(前編)」
「しばらく和花さん家に泊まっても良いですか?」
瑞姫ちゃんの突然の申し出に、私はえっ、と言葉を詰まらせた。
彼女は学生時代に所属していた旅サークルで、一番仲の良かった後輩である。歳は二つ下。けれど、すらっとした外見と知性に溢れた言動から、後輩よりも友達という感覚の方が強かった。私が大学を卒業してからも定期的に飲みに行っていたが、彼女の就職活動が始まってからというもの連絡を取っていなかった。
そんな状況下でかかってきた火曜深夜一時のコール。しかも声の端々は震えている。止むに止まれぬ事情があることは容易に想像できた。
「えっ、と……いいけど、急にどうしたの?」
ベッドから飛び起き、スマートフォンを耳に押し当てる。彼女は喉を引きつらせながら、ぽつりぽつりと事情を説明し始めた。どうやら、就職先のことで両親と揉めているらしい。やりたい職種で無事内定をもらっても、あまりよく知られていない企業名や規模感から親に反対されるというのは良くある話だ。けれど彼女の家庭はそれだけに留まらず、父親に土下座させられた上に陶器の湯飲みを頭に投げつけられたという。想像するとかなり痛ましい。彼女の父親がDVの素養があることは以前にも少しだけ聞いたことがあった。
このまま家に居たら殺されるかもしれないので、明日以降しばらく家出させて欲しい。そう訴えかけてくる瑞姫ちゃんに私は了承せざるを得なかった。「居たいだけ居て良いからね」とたまには先輩らしく彼女を慰めた。
電話を切ってから、再びベッドへ倒れ込んだ。仕事の疲労感は残っていたものの、目が冴えてしまった。仰向けになり、ぼんやりと天井を見上げる。家出、というフレーズが脳内を駆け巡った。
随分前のことだが、自分も一度だけ家出をしたことがあった。それも父親がらみで。と言っても私の場合は就職活動という人生において重要な時期なんかではなく、ただの大学一年生の夏休みだった。理由も特にない。強いて言うなら、大学生になってある程度自由が利くようになったことで全てから解放された気になり、いい子ちゃんでいることに嫌気がさしたのだ。とどのつまり、遅めの反抗期である。
当時のことが否応なしに蘇ってきて、私は電気を消した。タオルケットを身体に巻き付け、寝がえりを打つ。ベッドをくっつけている壁を目が慣れるまでじっと眺めていると、これより少し広いセミダブルで眠る彼の長い睫毛が思い出された。胸の奥が小さく疼く。私は目を閉じた。
翌日。仕事を終え、待ち合わせの二十時より少し前に渋谷ハチ公前広場へ着くと、瑞姫ちゃんが先に待っていた。私に気づくやいなや彼女は小さく会釈した。やたら大きな黒いバックパックの両紐をきつく握っている。少し痩せただろうか。ただでさえ色白の肌がいつもに増して青白く見える。
「和花さん。急にすみません」
「ううん、むしろ大丈夫?」
瑞姫ちゃんの顔を覗き込む。彼女は申し訳なさそうに何度も首を縦に振った。
私はニトリへ行こうと提案した。彼女が寝るマットレスを購入するためである。「えっ、そんな、床で寝るんでいいですよ」と瑞姫ちゃんはすぐ遠慮した。流石に女の子を床に寝かせるわけにはいかない。かと言って、夏場にシングルベッドで人と一緒に眠るのは正直私が辛い。元々来客用に買おうと思っていたし就活祝いだと思って、と瑞姫ちゃんを説き伏せ、私たちはニトリへ向かった。
ガラス張りの自動ドアを抜け、案内版で寝具売り場を確認してからエスカレーターに乗る。渋谷のニトリは思いのほか大きかった。「初めて来たわ~」とシャツの胸元を摘まみ上下させながら笑いかける。瑞姫ちゃんが「和花さんって、こだわり強そうだから家具とかちゃんとしたブランドで揃えてそうですね」と言った。残念ながら、家具のほとんどは通販と実家から持ってきたものである。
三階で降りる。奥まで歩いていくと、数千円のものから数万円もするものまで、多種多様なマットレスが置いてあった。私は瑞姫ちゃんと相談し、ベッドにも敷ける三つ折り式のマットレスを買うことにした。想定していた半分の値段だったので懐疑的ではあったが、「オンラインショップのレビューが一番良いです! お値段以上ですよ!」という彼女の熱意により、それにすることにした。
会計を終え、店を出る。ペトリコールの匂いと湿気を孕んだ空気に再び身を包まれた。エアコンで一度冷まされた熱が反動を伴って体外に滲み出す。普段なら一秒でも早く家に帰ってシャワーを浴びたいと思うはずなのに。隣で揺れる巨大な紙袋を見ていると、そんな気持ちも削がれていった。
「本当に家出したみたいです」
「みたいじゃなくて、家出じゃん」
「ですね。こんな大きなマットレス持って歩くの、ちょっと面白いです」
瑞姫ちゃんがくすくすと笑った。
渋谷から三十分ほどバスに乗り、最寄りのバス停で下車した。そのまま自宅近くのスーパーに足を運んで買い物を済ませ、私たちは帰宅した。
「ごめん、スリッパとかないんだけど」
家の鍵を開け、瑞姫ちゃんを中へ招き入れる。「お邪魔しまーす」とやや伺うような素振りを見せながら、彼女はそろそろと玄関で靴を脱いだ。私は彼女の持っていたマットレスを部屋の隅に運び入れた。クローゼットから座布団を一枚出し、簡易的な二人部屋にする。瑞姫ちゃんは部屋に入ってくるとすかさずビニール袋からビールの缶やつまみを取り出し、ローテーブルの上に並べた。洗面所で一緒に手を洗ってから部屋に戻る。改めて向かい合うとなんだか緊張してしまう。私は居住まいを正した。
「えーっと、とりあえず就活はひと段落したってことで。瑞姫ちゃん、お疲れ!」
私は缶を掲げた。瑞姫ちゃんは「すみません、ありがとうございます」と控えめに缶を合わせ、ビールを一気に煽った。彼女の飲みっぷりに私も負けじと缶を傾ける。開けたばかりのビールが乾いた口内に染み渡った。美味しい。そう浸りかけた時、瑞姫ちゃんが「親は私のこと本当に何も分かってないんです」と早速切り出した。
「私、昔からすごく引っ込み思案で、自分の考えや感情を上手く表に出せない子供でした。それがゼロとヒャクしかない父にはじれったく映ったんでしょうね。すごく怒鳴られて、ますます内気になりました。でも家族だし、親なんだから尊敬しなきゃと思って。いくら理不尽なことを言われても、黙って従うようになりました」
私は何度か瞬きをした。ビールを少し口に含む。
「それで?」
「それで、なんだっけ……あっ、母が病気になって入院することになったんです。そこからお父さんと二人で生活するようになって、暴力を振るわれるようになりました。私は怖くて、でも、お父さんも仕事のストレスとか溜まっているんだろうなと思って、納得して、殴られ続けました。それで最近、就活のことがあって、あれ、おかしいなって、思って」
虚空を見つめたまま、彼女は容量を得ない言葉をとうとうと吐き出し続けた。私は黙って聞いていた。親子の問題は、他人が薄っぺらいアドバイスをしてどうにかなるものではないから。
「やりたい仕事に就きたいって、そんなにダメなことなんですかね。なんか、何が悲しくて、何に怒りを感じているのかも、もう分かんなくって、そもそも、何で自分が生きているのか分かんなくなっちゃって……」
彼女が鼻を啜る。私はテーブルに置いてあった箱ティッシュをそっと彼女の近くに寄せた。すみません、と彼女はまた謝った。鼻をかむ音とタワーファンが回る音だけが室内に響く。私は再びビールを口に運んだ。ビールは一口目しか美味しくないと同僚の男の子が先週の飲み会で得意げに言ってきたけれど、私には何口飲んでも美味しく感じられた。
「親に就職浪人しろって言われてて、でも就浪したからと言って大企業に入れるわけじゃないじゃないですか。第一、私はそのランジェリーブランドの企画がやりたいのであって、何でも良いわけじゃないんです」
「うん」
「内定先にもお世話になりますって言っちゃったのに。就浪なんて絶対に無理……」
「分かる。瑞姫ちゃんの言っていること、よく分かるよ」
テーブルに缶を置いて私は頷いた。本当ですか、と瑞姫ちゃんが潤んだ目で私を見た。
「うん。私は途中で就活やめちゃったから本当は発言権ないんだけど。はっきり言って就職活動自体に一ミリのやる気も見いだせなかった」
「そう! 本当にそうなんです!」
急に瑞姫ちゃんが大きく身を乗り出した。その同調ぶりは、敵だらけで八方ふさがりの状況に一筋の光が差し込んだようだった。けれど、実際に体験してみるとそうなのである。
平成生まれのマインドと揶揄されたら意見しようがないが、就職活動は受験勉強のように気合で何とかなるものではない。確かにWEBテストや面接は練習をすれば多少は何とかなるのかもしれない。けれど、入ってしまったらそこで数年間は働かなければならないのだ。アルバイトと違って簡単にはやめられない。気に入らなければすぐに転職すれば良いという人もいるが、その無責任さで毎日働いている人はどれだけいるだろう。そこそこ気に入った仕事でないと続けるのが困難だ、ということは社会人二年目にして学んだ。
「そもそも私は周りみたいにあくせくしなくて就活を良いように数年かけて準備してきたんです。大学も推薦で、今回はインターン。そうやって狡賢く生きてきたんです。だから、私の就職活動における戦い方はこれが正解なんです」
そう言い切ると、彼女は残りのビールを流し込んだ。白くて細い喉元が大きく上下する。自信に満ちたその姿を見て、やっぱり瑞姫ちゃんはこの方が良いと思った。誰に対しても優しくて細やかな気遣いができるのに、大事なところは絶対に譲らない。そこが初めましての人事たちには見えていない、彼女の長所だ。
「これからも親は反対し続けるかもしれないけどさ、社会人になって一人暮らしとかするようになったらもう関係ないから。瑞姫ちゃんがやりたいと思ったことをやった方が良いと思うよ」
いかにも先輩という生き物が言いそうなアドバイスだな、と心の中で自嘲しながら、私は割り箸を手に取った。テーブルの上にはポテトサラダと枝豆と柿ピーが並んでいる。酒を飲んでいる時、私はあまり食べ物を口にしない。そしてそれは瑞姫ちゃんも同じだった。
「じゃあ、和花さんに一つ聞いてもいいですか?」
二本目のビール缶を開けながら、瑞姫ちゃんが訊いてきた。「うん、何でも聞いて」と返し、ポテトサラダをすくって口に運んだ。総菜なのにちゃんと茹で卵が入っていることが少し意外だった。
そういえば最近、家で初めて茹で卵を作った。卵を茹でるだけだから簡単だろうと高をくくっていたが、実際に作ってみると案外黄身が固まらず、一つ目はなんと温泉卵になってしまった。それはそれで美味しかったが、求めているものとは違う。そこで、もう一度お湯を沸騰させ、残っていた二つの卵を鍋の中に戻した。今度はきっちり六分、時間を計ってから取り出した。一つはやや黄身が緩かったが、最後の一つはオレンジ色の濃い理想の半熟卵になった。やった、とついガッツポーズをした。けれど、喜びも束の間。その頃にはもう二十三時を回っていて、卵を三つも食べてしまった罪悪感と激しい胸やけに襲われた。
この話を誰かにしたいと思っていたのに。今まですっかり忘れていた。折角だから瑞姫ちゃんに話してみよう。そう思い、私は全く脈絡のない話題を口にしようとした。その瞬間、瑞姫ちゃんが思い立ったように顔を上げた。
「あの、和花さんの初恋って、いつですか?」
(後半へ続く)

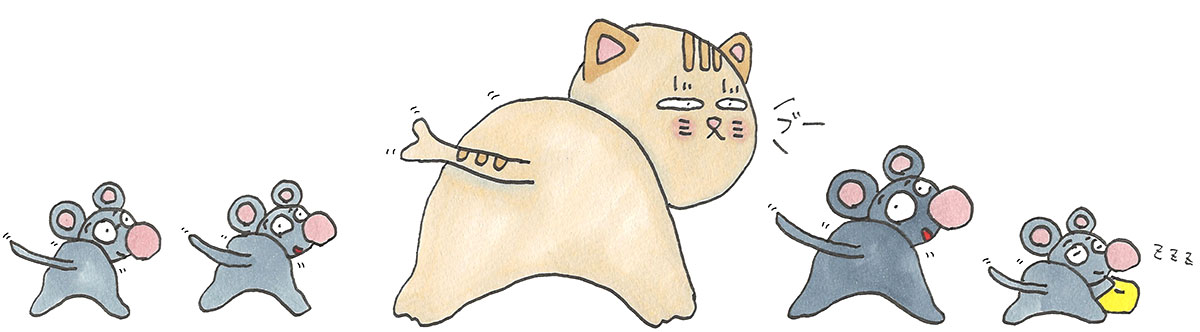









COMMENTS