「私のリョウくん」
私のリョウくんは、世間的に見て影の薄い人間だ。彼と面識がある人の中で、彼の顔をちゃんと覚えている人はそれほど多くないだろう。今だって、かけている黒縁の分厚い眼鏡に印象の全てを奪われてしまっている。どこかのメーカーが作った付属品にさえ負けてしまう男。それがリョウくん。けれど、そんなところもたまらなく愛おしい。
「……つまんない、かな?」
「え?」
何度か瞬きをした。いつの間にか、隣で映画を観ていた彼の横顔がこちらを向いていた。視線を汲むと、透き通った薄茶色の瞳が微かに揺れた。可愛らしい反応に、首筋の皮膚が熱くなる。ちょっとだけ、意地悪しちゃおっかな。下唇を舐める。
「つまんなくないよ。つまんなくない、けど」
「けど?」
トーンダウンを落とした私の顔を、彼が遠慮がちに覗き込んだ。そのぎこちなさは、彼が未だに女の子と近距離で話すことに慣れていないことをよく表している。けれど、いや、だからこそ、興奮する。今、彼の視界を支配しているのは私だけだ。
唾液でたっぷりと湿らせた唇を少しずつ開けていく。誘導された彼の視線は無意識にそこへ向かった。ラムネ瓶に入ったビー玉のような喉仏が上下する。その隙に、私は彼の背中へ腕を回した。服に着られているような痩せこけた身体なのに。リョウくんの背中は私よりずっと広くて、硬い。
沈黙に耐え兼ね、彼が口を開きかけた時、私は背中に手のひらを押し当てた。びくりと彼の肩が震える。予想通りの反応。にやにやせずにはいられない。手、冷たくてごめんね。心の中でそう謝ると、ゼロ距離になった彼の顔を見上げた。
「ねえ、リョウくん」
「なに?」
「……今日、リョウくんの家に来れて良かった」
「俺も。今日は花歩さんと二人でゆっくりできて嬉しい」
「本当? じゃあ……期待しちゃっていいのかな?」
「え?」
彼がまじまじと私を見た。私も見つめ返す。眠たげな彼の瞼が少し動いた。
やっと気づいたか。全く。こういうことは女の子から言わせちゃダメなんだよ。でも、そういう鈍いところもまた好き。
自分の方へ引き寄せるよう手のひらに力を込める。目を瞑ると、彼の熱を近くで感じた。生温い吐息と共に、柔らかな感触が私の唇を包み込む。しっかり重なったのを確認してから舌を伸ばすと、彼は優しく応えてくれた。
二十七年間、恋愛経験ゼロだったリョウくん。彼のファースト・キスをいただいた時は、こんなに拙く、幼いものかと動揺した。けれど、今ではすっかり私好みに成長してくれた。
舌を絡め合ったまま、薄く目を開ける。焦点の合わないぼやけた視界の中で、リョウくんの長い睫毛が揺れていた。
私の、私だけの、リョウくん。
ずっとこのまま、側にいてね。
リョウくんと付き合ったのは三ケ月前。でも、狙っていたのは、もっと、半年くらい前からだ。本名は久坂涼太郎。でもリョウタロウなんて長すぎるから、リョウくんってあだ名を付けて読んでいる。
彼は去年の四月、私が勤める会社にフロントエンジニアとして出向してきた。インターネットのセキュリティサービスをメインに行っているうちが外部からエンジニアを迎え入れることはそう珍しくない。しかし同時に、経理の私自体が専門職の人間と接点を持つこともほとんどなかった。だから、リョウくんの存在も八月の終わりになるまで実は知らなかった。
彼と初めて話したのは、同僚との飲み会の時。代り映えのしないメンツの中に、覚えのない顔があった。それはまるで、新学期にやってきた転校生の教科書が自分たちと違うような、ちょっと心がざわつく感じ。どうやら、同じエンジニア職の牧野くんが連れてきたらしかった。
「こちら、春にT社から出向してきた久坂さん。前まで俺と同じプロジェクトを担当していて仲良くなったんだ」
「久坂です。宜しくお願いします」
猫背気味の上半身がさらに折れ曲がる。T社と言えば、ソフト関係の最大手だ。当然、同僚たちは感嘆の声を上げた。
「久坂さん、本当に優秀な方で。本当に助かりました」
「いえいえ、むしろこちらこそ色々と教えていただいて。ありがとうございました」
「それより、久坂さん。あっちの方はどうなんですか?」
「あっち?」
彼が小首を傾げる。すると、牧野くんは「彼女ですよ、彼女」と下手くそなウインクをした。
「ほら、久坂さん今まで付き合ったことないって、言ってたじゃないですか」
「えっ、そうなんですか?」
他の同僚たちがT社以上に食いついた。彼らの目の輝きにたじろぎながら、彼は困ったような笑みを浮かべた。
その後、彼が周りから質問攻めされたことは想像に難くないだろう。けれど、それも一通り済むと、彼のお役は御免になった。社内の話題で盛り上がり始めた同僚たちの隅で、彼は居心地悪そうにちびちびと酒を啜っていた。私は人目を盗み、彼の前に席を移動した。
「さっきは驚いたでしょう」
人当たりの良さそうな話し方を選んで声をかける。最初、彼は自分に話かけていると気づいていないようだった。ややあって、彼は顔を上げた。
「あ……えっと、すみません」
「良いんです。ていうか、私のこと知らないですよね。こちらこそ急にごめんなさい。私、雨宮花歩って言います。経理部です」
「雨宮さん。久坂です、って、さっきも言いましたよね」
「言ってましたね」
笑ってそう返すと、彼とばっちり目が合った。実年齢は二つ上のはずなのに、血色の悪い肌と慢性的であろう濃いクマのせいでもっと老けて見えた。
けれど、この瞬間から、私はリョウくんのことが気になっていたんだと思う。事実、飲み会でLINEを交換して以来、私たちが連絡を取り合わなかった日は一度だってない。きっとリョウくんは女性と連絡を取り合うことが今までほとんどなかったから、切り時が分からなかったんだろう。彼の優しさに私は存分に甘えた。そして、何かと理由を付けては飲みに誘った。
リョウくんはああ見えてお酒が好きで、二人きりでいると色んなことを喋ってくれた。仕事の悩みも、家庭の事情も、今まで恋人がいなかった本当の理由も、知っているのは世界中で私一人だけ。そう思うと、余計に彼のことが欲しくなった。だから、私は酔った振りをして彼の手を握ってこうお願いしたんだ。
「好きって言って」
って。
リョウくんと正式に付き合い始めてすぐ、私は志保理に電話をかけた。志保理は社会人三年目に突入した今でも定期的に連絡を取り合う大学の同期で、リョウくんとの経過を唯一報告していた相手だった。浮かれている私に反し、彼女は納得のいかない様子だった。
「二十七歳の童貞とか、絶対に無理なんだけど」
「最初は誰だって童貞だし、処女じゃん。風俗も行けない辺り、リョウくんは誠実な人なんだよ」
「そう解釈する? ていうか、花歩は久坂さんのどこが好きなの?」
「全体的に好きだけど……強いて言うなら、冴えないところかな」
「何それ。あ、あれ? ライトノベルの主人公キャラ的な?」
「うーん、当たっているようで当たっていないかも」
「ちょっと。分かりやすく説明してよ」
「ライトノベルの主人公って、冴えないのにモテるでしょう? でも、リョウくんは私以外の女の子とほとんどコミュニケーションを取らないし、当然モテない。つまりね、ライトノベルの主人公も彼自身に魅力があるんじゃなくて、周りの女の子たちから寄ってってあげてるから成立しているのよ」
「……分かるようで分からないんだけど、それって結局、何もない村を開拓してイチから村を作っていく育成ゲームと同じ感覚?」
「まあ、そんな感じ」
「うわー。やっぱ、花歩の趣味にはついていけないわ」
電話越しに彼女が頭を抱えているのが目に浮かぶ。私はけらけらと笑った。
ライトノベルの主人公やら育成ゲームやらに例えられちゃうくらいだから、他人から見たリョウくんの評価はそんなもんなんだろう。別にいいよ。みんな、そうやってリョウくんを下に見ていれば良い。眼鏡を取ると意外と整った目鼻立ちをしていることとか、お茶碗の底に添える四本の指がぴったりと揃って綺麗なこととか、彼のパーソナルな部分を知っているのは私だけで良い。それに、付き合い始めてからのリョウくんは、目覚ましい進化を遂げている。服装も髪型もかなりマシになった。と言っても、彼は容姿に関して一切の興味がないから選ぶのはいつも私なんだけど。それでも、自分が好きなものを彼が身に着けてくれるのは誇らしかった。
これからも、これからもずっと、私だけのリョウくんだ。
……そう、思っていたのに。
見てしまった。リョウくんが、女の子と喋っているところを。
一年間の出向を終え、彼は再びT社で働くこととなった。離れ離れになってしまったけれど、社内恋愛で噂を立てられるのは面倒だと思っていたので、むしろ好都合だった。私は定時で上がると彼のオフィスがある渋谷へ直行した。退勤後のデートは、私が彼を迎えに行くのが慣習になっていた。
ガラス張りになったオフィスの広いエントランスに彼は立っていた。先に着いているなんて珍しい。リョウくん、と駆け寄ろうとして、はっとした。彼の隣には白いフレアスカートを履いた女の子がいた。
悔しいけれど、私よりずっと小柄で愛嬌のある子だった。リョウくんが何か言うと、彼女は楽しそうに笑った。心臓が嫌な音を立てる。今、リョウくんがあなたと自然にコミュニケーションを取れているのは私のおかげなのに。気安く笑いかけないで。
平静を保つべく、軽く深呼吸をした。そして、わざとヒールの音を立てて彼らに近づいて行った。
「久坂さん」
落ち着いたトーンで声をかける。私に気づいた彼は彼女に別れを告げると、早足でこちらへやってきた。
「ごめんね。邪魔しちゃった?」
「ううん、全然。さっきの女性、今年から第二新卒で入ったんだ。俺がOJTで面倒を見ることになって」
「へえ……そうなんだ」
口角を上げ、相槌を打つ。なんで先に言っちゃうかな。私が「あの子、誰?」って嫌味ったらしく聞く前に答えないでよ。リョウくん、女心が本当に分かってないんだから。
日の沈みかけた渋谷を並んで歩く。春になって夜になるのが随分遅くなった。
スクランブル交差点を渡りながら、「リョウくん」と私は話かけた。
「何?」
「……もしさ、AIが発達して、生まれた時からその人の性質や才能が数値化できるようになっちゃったら、その世界で私たちは出会うことができるかな?」
「え? なんで?」
身体を折り曲げ、聞き返す。私は彼を見上げた。西日に照らされた彼の輪郭はいつもよりくっきりと映えていた。それを見たら、なんだか悲しくなってしまった。
リョウくん、変わっちゃった。自分好みに変えたのは、私なのに。「男は女で変わるけれど、女は男で狂わされるだけなんだからね」と志保理に何度も釘を刺されたことをふと思い出す。分かってるよ、そんなこと。でもそんなこと言ったら、いつまで経っても恋なんてできないじゃない。
ふいに、視界からリョウくんが消えた。驚いて、私は辺りを見回した。すると、近くを歩いていた人たちが私の周りに輪を作るように退いた。彼らの視線を辿って、恐る恐る下を向く。すると、スーツ姿のリョウくんがアスファルトの上で無様に尻もちをついていた。
状況を把握した途端、全身の血が滾るのを感じた。羞恥だけではない、ある種のエクスタシーだった。綻びかける口元を引き締めながら、私は彼に手を差し伸べた。
「大丈夫?」
「ああ、うん。ごめん、ありがとう」
彼は恥ずかしそうに私の手を取った。あまり引っ張らずに自分で立ち上がったのは、彼の優しさとプライドからだろう。スーツの汚れを叩く彼の姿を横目に、にんまりと微笑んだ。
私の、私だけの、リョウくん。
ずっとずっと、この先も、可哀想なリョウくんでいてね。

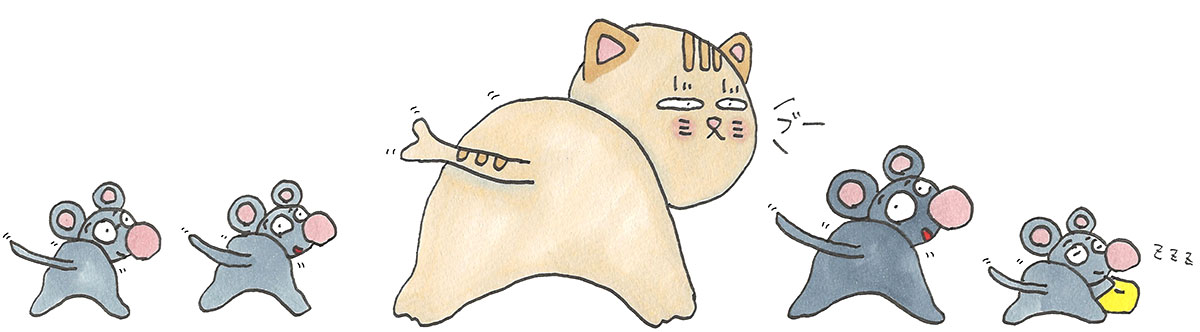









COMMENTS