「初夏の尋ね人(後編)」
「……え?」
思わず箸を取り落としそうになった。茹で卵なんかよりもずっと脈絡がない。
「……急にどうして?」
箸を握る指に力を入れながら、愛想笑いを浮かべる。アルコールのせいもあって、シャツまで浸透してしまうのではないかと思うほど脇の下がじっとりと汗ばむのを感じた。
「だって和花さん、恋愛の話ほとんどしないじゃないですかあ」
薄い唇を尖らせ、瑞姫ちゃんはだらしなく頬杖をついた。切れ長の瞳の端が潤んで赤くなっている。泣いただけでなく空きっ腹にビールを流し込んだせいで、早くも酔っ払っているようだ。そんなことないよ、と私は言った。
「ありますよ。だって和花さん、彼氏いた時も全然話そうとしなかったし。何なら、いつの間にか別れて違う人と付き合っていたこともあったじゃないですか」
「それは、なんていうか……第一、私の恋愛事情なんて聞いても面白くないでしょう」
「はい出た。そういうところですよ」
言質を取ったというように、瑞姫ちゃんは私に長い人差し指を向けた。
「ずっと思っていたんですけど。和花さんって、相手に対しての執着心が全くないですよね。女友達ならその方が気楽で良いと思うんですけど、彼氏ってなると話は変わってくるじゃないですか。執着心がないのに特定の相手と付き合うのって面倒じゃないんですか? でもその割に、コンスタントに彼氏がいたりして。それって周囲へのパフォーマンスなのか、告白とかされたら断れないだけなのか、それともその時その時では相手のこと好きなのか、かなり気になります。口悪くてすいません」
赤ら顔でまくしたてると、瑞姫ちゃんは一気にビールを傾けた。酒ってまだありますか、と訊かれたので、冷蔵庫の中の日本酒開けていいよ、と答えた。ありがとうございます、と彼女は会釈をし、ついでにトイレ借ります、と覚束ない足取りで席を立った。
部屋の裏側でトイレの扉が閉まる。瑞姫ちゃんがいなくなると、タワーファンの回る音が際立って聞こえてきた。ぬるくなってきたビール残りを啜りながら、彼女の言葉を脳内で反芻させる。正直痛いところをつかれてしまった。
しばらくして、流水音が聞こえてきた。トイレから出てきた瑞姫ちゃんが向かいにある冷蔵庫の扉を開ける。私は「私も飲むから食器棚の中からお猪口二つ持ってきて」と頼んだ。
瑞姫ちゃんは私の前にお猪口を置くと席に着き、慣れた手つきでお酌をした。彼女のアルバイト先は女将のいる、神楽坂の小料理屋だった。
黒塗りのお猪口を合わせてから、なみなみと注がれた日本酒を一口含んだ。少しずつ飲み下していくと、冷たい液体がかっと喉を焼いた。一息吐き、私はお猪口を机の上に置いた。
「……好きな人くらい、いたことあるよ」
やや投げやりな口調で私は言った。何の話、というように瑞姫ちゃんは顔をきょとんとさせたが、すぐに目を輝かせた。
「えっ、本当ですか?」
いつですか、と彼女が身を乗り出す。あまりの食いつきぶりに私はたじろいだ。
「えーっとね、大学一年の時かな」
「そうなんですか。なんか意外。どんな人だったんですか?」
「どんな人、かあ」
瑞姫ちゃんにせっつかれ、アルコールでぼんやりとする頭を必死で巡らした。もう数年前のことだ。全てを鮮明に覚えているわけではない。記憶を手繰り寄せ、彼の輪郭を思い起こしていった。
「私、大学入って最初に始めたアルバイトが新宿のカラオケ屋の店員だったのね。そこのバイトリーダーで……涌井さんって言うんだけど」
その名前を口にした途端、身体の内側が反射的に熱くなるのを感じた。瑞姫ちゃんに悟られないよう、話を続ける。
「彼は私の二つ上でね、大学三年生なのにほぼ毎日シフトに入っていたの。たまにそういう学生っているじゃない? 働くなんて社会人になればいくらでもできるのにって今なら思うけど、当時の私にはそれがすごく眩しく見えたんだよね。高校生から社会人に飛び級している感じがして」
綺麗に手入れされた金髪を耳にかける仕草が脳裏に浮かぶ。細くてさらさらとした直毛は彼の自慢だった。耳たぶに輝く小さなブルーサファイアのスタッドピアスも。バイトリーダーになったお祝いに買ったとかつて彼が教えてくれた。
「それで? その人とはどうなったんですか?」
「あはは、どうもなってないよ。だってその人彼女いたし」
「ええっ、そうなんですか?」
「うん。だから、片思いで終わったよ。はい、私の初恋の話はこれでおしまい」
私は腰を上げた。テレビ台の上に置かれたアナログ時計は既に十二時を回っている。明日のことを考えるともう寝たい。けれど、瑞姫ちゃんはそうはさせてくれなかった。
「えーっ、何それ。絶対嘘ですよ。だって和花さんみたいな他人の情に流されない人がたかがバイトリーダーってだけで好きになるとは思えないです」
酔った勢いで彼女が食い下がる。何が何でも最後まで聞きたいらしい。仕方ない。私は座り直した。
「その……確かに元々良いなとは思っていたんだけれど、バイトの休憩中とかで喋っていたら思いのほか意気投合しちゃったのね。それでそのうち、二人で飲みに行くようになって」
「わー、大学生っぽい!」
「でしょう。彼女さんに悪いなあとか思っていたけれど、バイトのことも含めてなんだかんだ毎日LINEもしていたから、私もつい期待しちゃってさ。そんな微妙な距離間のまま、たまたま涌井さんの家で遅くまで飲んでいた日にね、父親からメールが入ったの。内容は癌になったってことだった。まだ手術と抗がん剤で何とかなるレベルだったんだけど、その時はすごく動揺しちゃって。わあわあ泣いていたら、涌井さんが急に抱きしめてきたの」
そこまで話すと、瑞姫ちゃんが口元を両手で覆った。
「それで好きになっちゃったんですか?」
「うん。まあそんな感じ。もちろん、その後は何も進展しなかったから諦めるしかなかったんだけどね」
「だとしても超ロマンチックですね」
瑞姫ちゃんは嬉しそうに何度も頷いた。満足してくれたようだ。じゃあそろそろ、と促す。今度は彼女も素直に席を立った。
ローテーブルを隅に寄せ、空いたスペースに買ったばかりのマットレスを敷いた。予備の夏用敷きパッドを上から被せ、厚みを出す。そこに蕎麦殻の枕を置いて、来客用の夏布団をかけてやった。その間、瑞姫ちゃんは残った枝豆とポテトサラダを皿に盛り、ラップをかけて冷蔵庫の中にしまってくれた。
アナログ時計に目をやる。もう1時前だ。シャワーは明日の朝にしよう。
「布団、ありがとうございます」
「ううん。じゃあ電気消すね」
私はベッドに横になった。サイドボードに置いてあるリモコンに手を伸ばす。深夜まで煌々と白い光を放っていた照明は一瞬で消灯した。
仰向けになる。和花さん、と瑞姫ちゃんが私の名前を呼んだ。
「何?」
「……今日、和花さんの家に泊まって色々話せて楽しかったです。ありがとうございました」
「こちらこそ」
「おやすみなさい」
「おやすみ」
静まり返った室内にエアコンの微かな音だけが響き渡る。しばらくすると、彼女の寝息も加わっていった。一人残された私はぼんやりと薄暗い天井を眺めていた。ごめんね、瑞姫ちゃん、と心の中で呟いた。彼女にした話は、半分本当で半分嘘だった。
確かに私は涌井さんが好きだった。その涌井さんに彼女がいたのも本当だ。彼女の写真を見せてもらったこともある。派手なメイクで誤魔化した薄い顔は大して可愛くもなかったが、「あー、涌井さんってこういう女が好きだよな」と妙に納得してしまった。けれど、いやだからこそ、彼のことを諦めきれなかった。
私には十二時までに帰るという門限があった。実家暮らしの大学生ならよくある話だ。二十二時を過ぎると、父から『何時に帰る?』と決まってメールが入った。無視していると、二分おきに電話がかかってきた。瑞姫ちゃんの父親のように暴力こそ振るわないものの、気に入らないことがあると無言の圧力をかけてくる父のやり方が、私には嫌いで仕方なかった。この窮屈さから免れたい。そう意識するようになってから反抗期も増し、涌井さんと飲みに行くことも多くなった。ただ酒と男に逃げただけと言われたらそれまでだが、私なりの抵抗だった。
あの日――父から癌になったと告げられた日、私たちは新宿にあるチェーンの英国風パブにいた。何の話をしていたのかはよく覚えていない。ただ私は悪酔いして、意味もなく泣き出してしまった。ウザい女だ、と自分では思ったが、涌井さんは違った。対外的に困惑した表情を浮かべてはいるものの、ほろ酔いで濡れた瞳がじっと私の顔に注がれていた。イケる。そう直感的に確信した。だから私は涙交じりに彼に訴えた。今日は帰りたくないです、と。
その頃にはもう二十二時を回っていた。バッグの中のスマートフォンが頻繁に振動している。けれど私も好機を逃すわけにはいかなかった。涌井さんと指を絡ませながら店を出た。側から見たら、酔っ払った男女がじゃれ合っているようにしか見えなかっただろう。それでも何だか幸せだった。
彼の家に行くと、ベッドの上で私たちはお互いの身体を触り合い続けた。最後まではしていない。処女だったので、流れに身を任せて行う勇気はなかったのだ。
ひと段落して彼がトイレに立った時、私は自分のバッグからスマートフォンを取り出した。案の定、着信履歴がすごいことになっている。それも十二時を過ぎたところで途絶え、『何時に帰る?』とは別のメールが入っていた。それが癌になり、そのことを直接伝えたかったということだった。私は愕然とした。
「何かあったの?」
涌井さんに声をかけられ、はっとした。いつの間にかトイレから戻ってきたらしい。私は唇を震わせながら、父親が癌になったことを告げた。どうしてだか、涙は出なかった。
涌井さんは私の頭に手を回すと、自分の方へと引き寄せた。突き出た肩の骨がこめかみに刺さる。彼の身体は想像以上に痩せこけていた。ゆっくりと頭を撫でながら、「辛かったらしばらくうちにいても良いよ」と彼は言った。
それは一夜限りの優しさで、全然恋愛感情じゃないことなんて分かっていた。けれど、無性に縋りたくなってしまった。肉親が死んでしまうかもしれないのに。悲しい顔どころか、好きな男に慰められてむしろ喜んでいた。なんて薄情な女だ。ごめんね、瑞姫ちゃん。もう一度、心の中で謝る。私は瑞姫ちゃんよりもよっぽど狡猾で、ずっと動物的な人間なんだよ……。
瑞姫ちゃんの家出は一日で終わった。仕事から帰って来ると彼女の姿はなく、積まれた布団の上にはメモ用紙とコンビニの焼きプリンが置いてあった。そこには『もう一度、両親と話し合ってみます。泊めていただきありがとうございました。また飲みましょう!』という綺麗な文字が並んでいた。やっぱり瑞姫ちゃんも優等生だな、と思った。
寝具を片付け、部屋を普段通りに戻す。たった一日だけだったのに。彼女がいなくなった部屋はなんだか広く感じた。とはいえ、このまま居座り続けられても正直困ったのだが。
ローテーブルに着き、私は焼きプリンの上蓋を剥がした。焦げのついたしわくちゃの表面を銀色のスプーンの腹でなぞる。そういえば、最後に見た涌井さんの髪色もこんなだった。
「このままバイトで就職でもいっかな~」と散々言っていたのに。就職活動が始まる頃には自慢の金髪も不自然な黒に染まっていた。ブルーサファイアのピアスももう付けていないだろう。そんな彼と街ですれ違ったとしても気づける自信はない。
私はプリンを口へ運んだ。滑らかな固形物は舌の上で溶け、ほろ苦い後味だけを口内に残した。
(完)

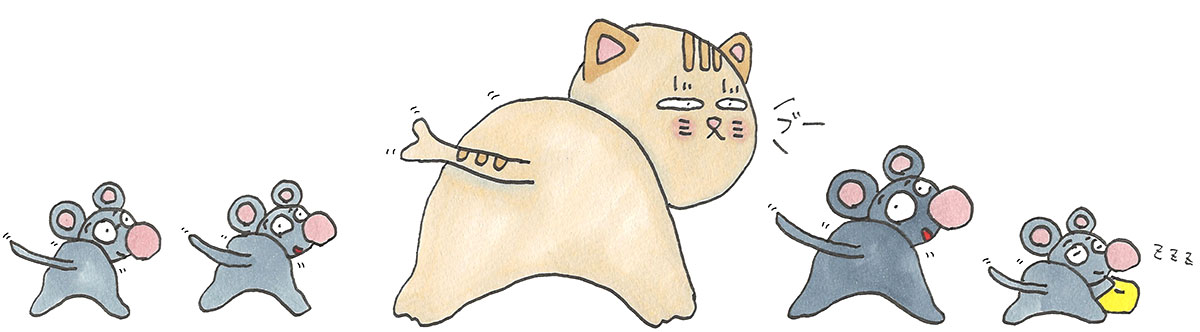









COMMENTS