「準備は念入りに」
「あたしさ、ヤったんだよね」
朱華にそう告げられたのは、高校二年生の夏休みだった。確か終わりの方だったと思う。当時の私はインターハイや選抜で毎年成績を残している強豪ソフトボール部に所属していて、日々練習に明け暮れていた。おかげで夏休みらしい夏休みはほとんどなく、彼女の家で宿題を写させてもらうことに楽しみすら覚えていた。
部員の愚痴、顧問の愚痴、最近ハマっているドラマの話……いつもと変わらないはずの日常会話。そこへ放り込まれた何気ない爆弾発言に、私の心臓はドキッと跳ね上がった。丸バツを付けていた手がつい止まる。水性の赤いインクがペン先を中心にノートへ深く深く滲んでいった。
「……ヤったって、あのヤっただよね?」
妙に開いてしまった間をなかったことにするように、私は前の会話と同じ口ぶりで尋ねた。努めて自然な動作でペンを置き、彼女の様子を伺うように顔を上げる。うん、と朱華は頷いた。
「え、誰としたの?」
「えっとね……えっと、誰にも言わない?」
「うん」
やや食い気味に答える。朱華は机の上で組んだ両手に視線を落とした。
「SNSで知り合った人。メッセージでやり取りしていたら、意気投合して直接会いましょうってなったの。普段は出版社で働いているんだって」
「そうなんだ。その人とは初めて会ったの?」
「ううん。三回目、かな」
「どんな感じなの? やっぱり痛いの? 血は出た?」
「うーん、こんなもんかあって感じ。結構痛かった。血は……分かんない。その、公衆トイレでヤったから」
そう言うと、彼女は急に頬を紅潮させた。まんざらでもなさそうな表情が若干鼻についたが、正直どうでも良かった。決して中高一貫の女子校に通っていて、そちらの方面に無縁だったからではない。むしろ人一倍興味はある。だからこそ「なんで?」というシンプルな疑問が脳内に溢れかえっていた。理由は単純。朱華がブスだったからだ。
自分の面目のために言っておくが、朱華が可愛くないということは私だけの基準ではない。同級生内の暗黙の了解だ。けれど朱華は持ち前の狡猾さでスクールカースト上位の人間たちに上手く取り入っていたから、みんな大っぴらに口に出すことはなかった。ただ容姿の話になると「朱華ちゃんは……うーん……」と口ごもった後、「可愛いっていうよりは、美人顔だよね~」と訳の分からないフォローをして、にやにやと笑い合う。そんな格下の彼女が炎天下で血の滲むような努力を強いられている自分を差し置いて、女としての地位を確立している。その状況が全く受け入れられなかった。
高校三年生の夏。全日本高校女子選手権大会でベスト4入りを果たした私は中高の青春に幕を閉じ、翌日から受験勉強に勤しんだ。部活動に一生懸命だった人は切り替えも早いし集中力もあるから大丈夫よ、と担任に励まされたが、私が頑張るのは決して良い大学に入るためではない。それはあくまで通過点だ。本当の目的は、朱華よりずっと素敵なセックスをするためだった。あの日以来、私はセックスがしたくてしたくて仕方がなかった。というより自分が朱華よりも動物として劣っているとはどうしても思えず、それを証明する必要があった。
必死で勉強した結果、私は第一志望の理系私大に合格した。大学生になった私はすぐにアルバイトを探し始めた。職種は何でも良かったが、新宿で働きたかった。キャンパスの最寄り駅からJR中央線の快速電車で十分とアクセスが良かったし、繁華街で人が多いので、素敵なセックスをしてくれそうな殿方を探せる確率が高いと踏んだのだ。同じ大学の人間が悪いというわけではない。ただ朱華が社会人と寝たと言っていたので、私も張り合う、いや、それ以上の人を捕まえたかった。悩みに悩んだ末、私は新宿三丁目駅直結の百貨店内にあるスマートフォン・ショップのサポートスタッフとしてアルバイトをすることにした。
アルバイト初日、自前の白いワイシャツと黒いパンツに身を包み、『研修中』というバッジを胸に付けた私はサポート担当の先輩スタッフを紹介された。その人は小出さんと言って、同じ大学出身の新卒四年目だった。色白の丸顔に黒縁の丸眼鏡と整えられた顎ひげ、ワックスで前髪を軽くかき上げた赤茶けた短髪。長身なのも相まって、ここのブランド創設者に少し似ていた。笑うと眠たげな目が糸のように細くなって可愛い。柔らかな白とナチュラルウッドを基調とした気品溢れる店内とも良くマッチしている。この人にしよう、と私は心に決めた。
そこからは学業とアルバイトに打ち込んだ。小出さんとセックスをするためには、とにかく接点を増やして仲良くなるしかない。私はアルバイト用にノートを一冊作り、教わったことをどんどんメモしていった。就業時間が終わって家に帰る間、ノートを見返して復習をし、分からないことは次のシフト時に尋ねた。異常なほどの熱心さだったが、小出さんは嫌な顔一つすることなく、むしろ嬉しそうだった。半年経つ頃には、正社員とほぼ同じサポートが滞りなくこなせるようになっていた。当然、私と小出さんの距離も縮まっていき、就業終わりによく飲みに誘ってくれるようになった。
「それでさ、俺の寝ている間に彼女が指紋認証のロックを解除してスマートフォンの中身を盗み見ようとしたんだよ。ありえなくない?」
ハイボールを呷りながら、小出さんは苛立ちを抑えきれない様子だった。彼には学生時代から付き合っている彼女がいた。週にどのくらいセックスするんですか、と常々尋ねたいと思っていたが、私の前では彼女の話をあまりしたくなさそうだったので憚られた。彼女のことを自ら話題にするのは今日が初めてだった。
「あー、それはちょっとないですねえ」
「だよねえ。ハァ、マジでしばらく会いたくないわ」
眼鏡を取って片手で顔をこする。疲れのせいか怒りのせいか、早くも真っ赤になっていた。眼鏡をかけ直し、小出さんは話を振った。
「ていうかさ、相庭ちゃんは? 彼氏いないの? そういう話って普段しないよね」
お、なんか見たことある展開、と心の中で呟く。小出さんのペースに合わせてウーロンハイを口にしながら、私は首を横に振った。
「えー、いないですよ」
「なんか意外。モテそうなのに」
「全然モテないですよ。中高とも女子校だったので、彼氏すらいたことないです」
両手で持ったグラス越しに見やる。私の言葉に小出さんはふぅんと芯のない相槌を打った。
二十二時過ぎ。私たちは居酒屋を出た。いつもならこのまま他愛ない話をしながら新宿駅に向かう。けれど、彼の足取りはやけに重い。小出さん、と私は声をかけた。すると、彼は
「……ねえ、ホテル行かない?」
と尋ねた。
この台詞を半年、いや、丸二年間どれだけ待ち詫びていたことだろう。本来であれば、逆転サヨナラホームラン並みに歓喜の雄叫びを上げているところだ。けれど、いざその瞬間が訪れると緊張感の方が勝った。私は「はい」と答えるので精いっぱいだった。
私たちは途中で横断歩道を渡った。歌舞伎町と書かれた真紅のネオンがギラギラと光るアーチを潜る。こんな時間なのに多くの老若男女が行き交っていた。昼間の世界とは全然違う。ネオンに負けないくらいぎらついた眼差しと脂ぎった匂いを醸し出す人々は、人間の皮を被った二足歩行の動物みたいに思えた。
彼に手を引かれ、リゾートホテルみたいなラブホテルに入った。店内は広く、シャラシャラと細い鎖がぶつかり合うような涼しげなBGMが流れている。事前に調べていたラブホテルと全く異なっていて、きょろきょろと辺りを見回してしまった。対して小出さんは慣れた様子で受付を済ませた。鍵を受け取ると、「行こうか」と私の肩を抱いて促した。
部屋は五階の角部屋だった。ハリウッドミラーのついた大きな洗面所と言い、天蓋ベッドと言い、そこら辺のラブホテルよりグレードが高いことは私でも分かった。「初めては良い思い出の方が良いでしょ」と小出さんは笑った。
「先、シャワー浴びる?」
「え、良いんですか」
思わず聞き返してしまった。ネットの情報によると、シャワーを浴びる前にベッドで一悶着あると書いてあったからだ。それを見越して、勝負下着の装着はもちろん、ムダ毛処理も終えている。この二つは小出さんといつ何時そうなっても良いように習慣づけていた。私の返答に小出さんは意外そうな表情を浮かべたが、「じゃあ、少し触ってからでも良い?」と訊き直してくれた。
白いシーツのかかったダブルベッドに小出さんは座った。その上に私を向かい合って座らせる。長身の彼とようやく目線が合った。
「目、閉じて」
私は従った。視覚を奪われるとその他の感覚が鋭敏になる。髪を梳く彼の大きな手が心地良い。頬に彼の熱を感じた。下唇をそっと舌で撫でられる。ぬるりとした感触に背中がぞくぞくした。
小出さんは私の唇や顎、首筋へとキスを降下させながらも、背中を弄る両手は徐々に上昇させていき、ワイシャツ越しにブラジャーを外した。器用だなあ、と他人事のように思った。ボタンを上から順に外し、ワイシャツとブラジャーを取り払った。オレンジ色の仄暗い明かりの下、私の輪郭が浮かび上がる。綺麗だね、と小出さんは呟いた。
「このまま続けて良い?」
「……はい」
彼は私をベッドに押し倒し、シャツを脱いだ。線の細い身体は想像通りだった。彼が私のパンツに手をかける。咄嗟に目を逸らした。自分のあそこを見られるのも、彼の膨らんだ股間を見るのも耐性がなかった。
触る舐めるを繰り返され、事が進んでいく。初めての体感に気持ち良いのかくすぐったいのか判断つかなかった。けれど彼は興奮しているらしい。握らされた陰部は確かに勃起していた。硬さや太さ以上に人肌とは思えないほどの熱さに驚いた。指に思わず力が入る。すると海の生き物みたいにぴくりと動いた。面白くなって、私は手を動かした。小出さんが息を漏らした。
「ごめん……一回挿れていい?」
シャワーを浴びなくて良いのだろうか。疑問に思ったものの、この雰囲気を壊すわけにも行かない。黙って頷くと、小出さんはベッドボードから備えつけのコンドームを一つ手に取った。哺乳瓶の先を小さくしたような形状を眺める。いよいよするのだなと思った。私の緊張が伝わったのか、彼はやや躊躇する素振りを見せた。けれど、彼も彼で余裕がないらしい。「痛かったら言ってね」と治療前の歯医者さんみたいな台詞を吐いた。
湿っている挿入口を再度ほぐし、私の両脚を腕に引っかけた。そのまま陰部をゆっくりと押し込んでいく。内部が割かれていく痛みが走る。うっと呻いた。
「大丈夫?」
なわけない。けれど、ここでやめてしまえば、出産なんて耐えられるはずがない。
「力抜いて」と声を掛けられる。入りますように、と私は真面目に祈った。
彼は私の腰を持ち上げた。そして今度は挿れるのではなく、私の入り口にあてがった。しばらくして、異物が侵入してくる感触を覚える。圧迫感はあるものの、痛みはそれほどなかった。
「大丈夫?」
「大丈夫ですけど……変な感じです」
そう言うと、彼はほっとしたようにキスをした。
高級ラブホと優しい男。二年間準備してきただけあって、割と素敵な初体験を送ることができた。少なくとも公衆トイレで処女を捨てた朱華よりは、ずっとだ。それなのに、あの時の朱華と同じ感想を抱いていることに気づいてしまった。必死で腰を動かす彼を目の前にしながら、私はにやけずにはいられなかった。
……こんなもんかあ(笑)
(完)

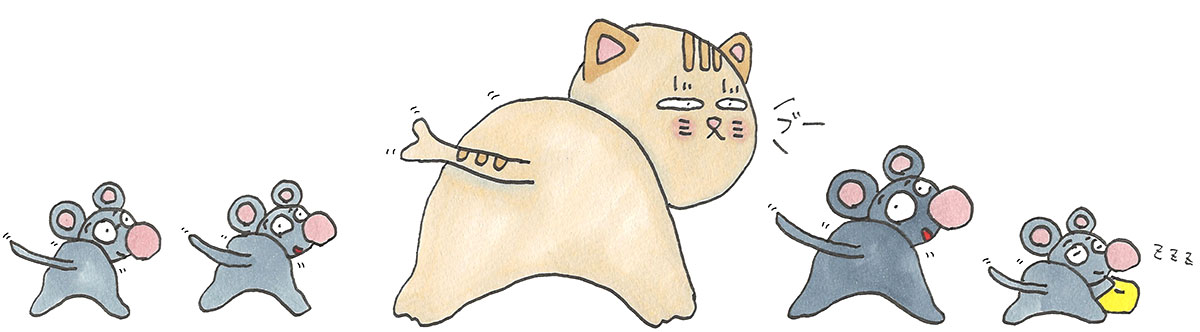









COMMENTS