「午前2時の女たち」
耳の中でパァン、と乾いた破裂音がした。それは普段の私とは全く無縁で、テレビドラマなんかでしか聞かないものだったが、この歌舞伎町という街によく合っていた。ぎらついたネオンなんかより、むしろこっちが本当なのだろう。常に危ない匂いを肌では感じるものの、実際に何かが起こることはないから、いつしかその刺激にさえ慣れた猛者のように振舞っていた。ただ平和ボケしていただけだということも知らずに。
持っていた漫画が無意識に手から離れた。足元でバサバサと紙束が落ちたが、どうでも良かった。右耳のイヤフォンに指を当てる。このインターネットカフェは、ゴジラがいる映画館の裏にある。そのせいで、斜向かいの歌舞伎町交番の無線をインカムがたまに拾ってしまうのだ。息を押し殺し、耳の中の音に集中する。ノイズの後ろから男性が何かを指示しているのが聞こえた。走っているのだろうか。呼吸が荒く、声も安定しない。身体の中に流れ込んでくる音が私の心拍数を上昇させる。瞼の裏に浮かんだ情景に気持ちが引っ張られそうになったその時、肩に柔らかい感触を覚えた。はっとして振り返ると、智草さんがいた。
「大丈夫?」
長身の彼女が少し腰を折って私の顔を覗き込む。私は黙って頷いた。一気に血が引いていくのを感じる。彼女は平気そうだった。何なら、少し楽しそうだ。
「全然ニュースにならないけれど、最近多いのよね。この辺って、中国マフィアとか多いじゃない? 彼らの内部抗争か何かでも起こっていそうよね」
そう事もなげに話すと、頬に手を当てた。ゴールデン街近くのガールズバーと掛け持ちして働く彼女にとって、この手のネタは日常茶飯事なのだろう。けれど、生涯のほとんどを表の世界で過ごしてきた身としては、知る由もない。私は何も言わず、曖昧な笑みを浮かべた。智草さんにはそうすることが正解だったからだ。相手の答えは一切求めていない。事実、彼女は喋るだけ喋ると、「困ったことがあったら言って。いつでも相談に乗るから」とお決まりの台詞で会話を締め、清掃しかけの持ち場へ戻っていった。彼女が入っていた個室をしばらく眺めた後、私は漫画を拾った。まだ心臓が早鐘を打っていたが、幾分かマシになっていた。
ここで短期アルバイトを始めて二か月と少し。前の職場に疲れて半ば勢いで退職し、転職先が決まるまで繋ぎで始めたものだった。次は予想以上に早く決まってしまったが、来月まで入社を待ってもらうことにした。すぐに働く気にはなれなかったし、これはこれで学生に戻ったみたいで新鮮だった。
漫画を順番に棚へ並べ終え、私は同じフロア内の受付へ戻った。夢未ちゃんがいた。制服の黒いワイシャツに身を包んだ彼女の背筋は、こんな丑三つ時でもすっと伸びている。しかし、俯いた視線はカウンターの下に注がれ、その先にはスマートフォンが垣間見えた。この時間にもなると、もちろん人は来ない。監視カメラで接客の様子が映し出されてしまう以上、体裁を整える必要があるのだ。深夜に受付をするアルバイターのほとんどがこうして時間を潰していた。私は彼女にそっと歩み寄った。「今日はいい男見つかった?」と尋ねる。夢未ちゃんは「全然ですよお」と口元をへの字にした。
「相変わらず、ゴミばっかりなの?」
「ですね。ていうか、マッチングアプリで出会いを探している男は、よっぽどのことがない限り負け組ですよ」
そう言いながらも、懲りずに続けている。彼女曰く、これはリアルイベントが発生するソーシャルゲームと相違ないようだ。画面を見ながら、夢未ちゃんは呆れたように笑った。
「負け組だからこそ、彼らって理想は高いんですよね。本当、馬鹿ばっかりです」
「あはは、言うねえ」
「事実ですから。例えば、この人。見てくださいよ」
彼女が青白い画面を私に見せてくる。そこには男の写真とハンドルネーム、それから簡単な自己紹介が載っていた。文面によると一夜限りのセックス目的ではなく、真面目な交際を望んでいるらしい。
「これは、出会い系の中では良さそうな方じゃないの?」
「愛子さん、マジで言ってます?」
夢未ちゃんが引いた目を向ける。
「こういうのが一番厄介なんですよ。ほら、ここ。見てください」
ピンクベージュの清楚なジェルネイルが施された爪で画面を軽く叩く。『好きなタイプは、気遣いのできる女性・何かを頑張っているタイプの女性』と書かれていた。
「これのどこが厄介なの?」
「普通のことを言っているように思えるかもしれませんけど、気遣いができる女性が好きって書く男はヤバいです。こういう人って出会い系に限らず、自分のプライベートに必要以上に踏み込んで来るなって暗に言っているようなものですから。それなのに彼女が欲しいって、都合よく愛してくれる女が良いってことなんですよ。それと、何かを頑張っている女性が好み。私の経験則ですけれど、こういう人はリアルだと大抵口ベタです。彼女が欲しいくせに、女の子を楽しませる努力はしない。一番疲れます」
夢未ちゃんが溜息を吐いた。
「気を遣って、頑張って、僕のことを気持ち良くしてくださいって、ただでさえ負け組なのに、救いようなさすぎますよね。本当、こういうやつを見ると、虫唾が走るので、精神的に追い詰めてやりたくなるんです」
悪い顔をして彼女は吐き捨てた。まだ学生三年生なのにこんなところで長く働いているから、歌舞伎町という空気に心まで浸食されてしまっているのだろう。
「愛子さんもやってみたらどうですか? マッチングアプリ」
白い歯を見せて彼女が言った。
「看護師なら、全然余裕ですよ」
その台詞に、私は思わず苦笑した。
「次の職場でも看護師でしたよね?」
丸い目をパチパチと瞬かせて訊いてくる。私はそうだよ、と答えた。
「いいなあ。温室育ちの金持ちドクターがいっぱいいそうじゃないですか」
夢未ちゃんが羨ましそうに目を輝かせた。脳裏にあの時の光景がふと過ぎる。私は反射的に視線を落とした。
「……休憩もらうね」
そう言って、彼女の横をすり抜けた。何も知らない彼女は、はぁい、と気の抜けた返事をした。
スタッフルームの奥の扉を押し開け、非常階段の踊り場へ出ると、冷たい風が頬を撫でた。十月に入って夏の残滓はすっかり失せ、冬の足音が刻一刻と近づいていた。シャツの襟を合わせ、もう一方の手をパンツのポケットへ入れる。中から煙草とライターを取り出した。東京都の条例で屋内が全面禁煙になったことで肩身は狭いが、ここは吸う人が多いのか、スタンド灰皿が設置されていた。
煙草に火を点ける。肺を膨らませ、唇の端からゆっくりと息を吐いた。紫煙が雲一つない透き通った夜空へ溶けていく。ここなら中国マフィアの抗争を生で聞けるんじゃないかと期待したが、酔っ払った若者の黄色い声以外は何も聞こえなかった。ぼんやりと虚空を見つめたまま、あの時のことを思い出す。
「愛子のことはもちろん好きだよ。けれど、絹江も俺にとっては大事な存在なんだ」
そう困ったように説明をする明彦の表情が未だ脳裏にこびりついている。もう二か月以上も前のことなのに。取っても取っても出てくる排水溝の髪の毛のように、私に絡みついて離れない。
明彦は、院内でも優秀な内科医だった。いや、今でもきっと優秀な人材だろう。彼は人を助けることが自分の使命だと当たり前のように思っている。その正義感は医者として素晴らしいことだが、時として近くにいる人を深く傷つける。私たちの婚約は、絹江さんを救ったことにより破談してしまった。
絹江さんは明彦の学生時代の彼女だ。就職活動に失敗して留年したものの上手くいかず、大学卒業後は旅行会社の派遣をやっていたらしい。精神的に弱い人だからと明彦は言っていたが、単純にやる気の問題だと私は思う。そうでなければ、派遣に切られて数年連絡を取っていなかった元彼の家に転がり込んで来る図太さはない。次の就職先が決まるまでということだったが、今の情勢と彼女のメンタリティを考えると決まるはずもなく、ただ二人で住む時間だけが延長されていった。それと同時に、明彦の家に彼女の生活臭が滲み出るようになり、やがて馴染んで二人の空間へと変貌していった。リビングのゴミ箱に使用済みのコンドームが捨てられていたのは、そんな頃だった。
男女が一つ屋根の下に住んでいてないことはないと思っていたが、いざ現実を突き付けられると辛い。このネカフェもそうだ。料金を払った時間まで滞在した彼らは、個室に湿ったティッシュやゴムを残して帰る。酷い時は床に放置されっ放しになっていることもある。少し歩けばホテル街なのに、と思いながら、私はその痕跡を無感情に消す。次の客を迎えるために。そうしてまた汚され、掃除するを繰り返す。
アルバイトだったらそれができるのに、恋人となるとそうもいかない。だから、私は明彦にゴムのことを問い詰めた。正義感の強い彼なら反省し、二度と同じ過ちは繰り返さないと約束してくれると思った。けれど、違った。彼は謝罪の色を見せることはなく、それどころか、他人の家のゴミ箱を漁るなんて、と逆上してきた。ああ、と私は思った。夢未ちゃんの言葉を借りれば、彼も都合よく気遣いのできる女が好きだったのだ。
馬鹿馬鹿しくなって、私は彼に別れを告げた。後になって彼は病院で幾度となく謝ってきたが、私の気持ちが再燃することはなかった。やがて顔を合わせるのも苦痛になり、私は病院を辞めた。
煙を肺に流し込みながら、壁にもたれかかる。
この街に流れ着けば、何かが分かると思っていた。どんな人間でも飲み込み、受け入れる。歌舞伎町はそういう街だと思っていた。けれど、実際は受け入れているのではなく、ただ黙認しているだけだった。全ては虚構。堕ちるも離れるもあなた次第。そういうことに勘良く気付いてしまう私は、落ちることも染まりきることもできない。ネットカフェという同じ空間で歌舞伎町に住まう彼らと同じ行動を取ったとしても、ただ違和感だけが残ってしまう。とどのつまり、自分の行き場なんてどこにもないのだ。
「それでも、私はあなたの人生の暇つぶしにはならない」
思わず言葉が口から漏れた。それは煙に乗って宙へ伸びていく。二本の頼りない灰色の線を眺めながら、まだまだ夜は長いなと思った。
(了)

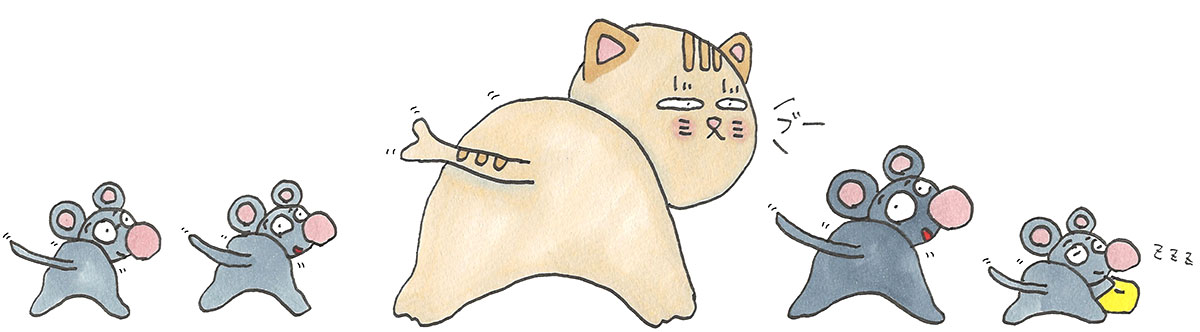









COMMENTS
たまたま広告から流れてきて、たまたま目に付いたタイトルに惹かれ、たまたま同じ名前の主人公に掴まれ一気に読んでしまった…!文がとても良いぃ泣。小説が読みたくなりました。どなたが書かれているんだろう。