「ふたたび」
雲一つない真っ青な空の中心で、冬の太陽がギラギラと輝いている。二月でも温かいとは聞いていたものの、これほどだとは思っていなかった。東京の肌感覚で言うと初秋。歩いているだけで脇や額に汗が滲む。潮風による寒さ危惧して選んだ薄手のタートルネックをやや後悔しながら、私は辺りを見回した。オフシーズンだからか平日だからかはたまたその両方だからか、人影は殆どない。緩やかに蛇行をする白い石畳の通りと、それに沿って左右に立ち並ぶ背丈の低い年季の入った建物には柔らかな午後の陽射しが降り注ぎ、そこだけ時が止まっているようだ。まるで身に覚えのないいつかの夏休みを彷彿とさせる。少し違和感を覚えるのは、ところどころで目にする赤い瓦屋根くらいだろう。強風に備えて平たい瓦と丸い瓦を漆喰で塗り固めて作った特徴的なそれは『琉球瓦』という名前だと、昨日Google先生で調べて知った。
暑さでつい明後日のほうを向いてしまう意識を引き戻そうと、店の軒先へ再度目を移す。隣では千波が真剣な眼差しでやちむんを選定していた。
沖縄に来るのは人生で二度目だった。一度目は高校二年生の時の修学旅行。けれどそれは手放しに楽しめたものではなかった。というのも、四泊五日中の最初の二日間が第二次世界大戦時の沖縄について学ぶ、平和体験学習だったからだ。それが修学旅行のメインイベントであることも、戦争を体感していない世代として知っておくべきだということも、もちろんよく分かっていた。けれどあの時平和祈念資料館で見た、無数の人間の死体が崖を転げ落ちていく映像やはらわたの飛び出た子供のモノクロ写真によって、出された郷土料理はどれも味がしなかったし、翌日のガマ体験では霊感の強い子が座り込んだり泣き出してしまったりして大惨事だった。帰りの飛行機の中、私は隣に座る千波に「全然楽しくなかった」と文句を垂れた。最終日の自由行動で疲れ果て殆どの生徒は爆睡していたが、千波だけは唯一起きて本を読んでいた。彼女は私の発言を聞き、「じゃあ、大学生になったらまた来ようよ」と返した。予想していなかった台詞に面食らいつつも、すぐにOKした。一度きりの旅行で沖縄はつまらないと偏見を持ちたくなかったし、何より千波と旅をするのは楽しそうだ。私にとって彼女は最も気の合う友人で、大学こそ違ったものの、数ケ月に一回は会って飲んだり遊んだりしていた。大学の課題やサークル、アルバイトの都合などで長期休みの予定がなかなか合わずにいたが、卒業を一か月後に控えた学生最後の春休みを機にようやく決行することとなった。五年越しの修学、いや、卒業旅行。テーマは、『五年前ではやれなかったことを存分に楽しむ』旅。その二日目はやちむんのマグカップが欲しいという千波のリクエストで、壺屋やちむん通りへ出向いていた。
「結奈、結奈」
名前を呼ばれ、我に返る。知らないうちに彼女は三軒ほど先に進んでいた。なあに、と小走りで駆け寄った。
「これ見て」
店の前に出された木製の白い立て看板を千波が指差す。そこには茶色の丸文字で『陶芸体験』というペインティングが施されていた。
「やってきたら?」
「え?」
唐突な提案に思わず彼女を見る。「だって結奈、陶芸習ってたじゃん」と千波は長い睫毛を瞬かせた。それはそうだけど、と口ごもる。
「千波はやらないんでしょ?」
「うん。あたしは不器用だから、お店のやつ買う」
「それなら待ってもらうの申し訳ないよ」
「良いって。今回はやりたいことをやる旅なんだから。それにあたし、結奈が陶芸やってるの見てみたいな」
大きな瞳を輝かせて彼女は微笑んだ。そんな表情をされてしまうと断るに断れない。立て看板にもう一度目をやりながら、「じゃあ……やってみるよ」と渋々頷いた。
今まで見てきたお店と同様に、店内には器やお皿など様々なやちむんが置かれていた。女の子が好きそうなカラフルで可愛らしいものというよりは、焼き物の素の色を活かしたシンプルで正統派な作品が多い。いらっしゃいませ、と年配の女性が愛想よく近づいてきた。
「今から陶芸体験できますか?」
「できますよ。ロクロと手びねりと絵付け、どれになさいますか?」
「ロクロでお願いします」
「仕上がりまでに一、二カ月くらいかかるんですけど、郵送とご来店でのお受け取りどちらになさいますか? 郵送の場合は別途料金がかかります」
一、二カ月後に再訪する予定は今のところない。郵送でお願いしますと言うと、レジカウンターで伝票を渡された。必要事項を記入し、料金を払う。
「ありがとうございます。それでは、ここから百メートルくらい先にある工房に向かってください。お店を出て右手に矢印の標識がありますので、それを辿っていけば分かると思います」
店を出た。彼女の言う通り、小さな看板が柱に釘打ちされていた。『工房はこちら』と矢印が書かれている。それに従い、私たちは路地へ入っていった。
工房は急こう配な坂道の途中にあった。開け放たれた門の先に座る大きなシーサー二匹が私たちを出迎える。勝手に入って良いのか分からず戸惑っていると、三十代半ばくらいのお兄さんが工房からひょっこり顔を覗かせた。
彼に招かれ、工房に足を踏み入れる。湿気を含んだ土の匂いが鼻孔を擽った。懐かしい香り。少し緊張する。
「初めてですか?」
作業用のエプロンを着け終えると、彼が訊いてきた。
「あ、えっと、少しやったことがあります」
「そうですか。じゃあ、土殺しからやりますか?」
土殺しとは、ロクロ成形で最初にやることだ。これによって粘土の密度が均一になり、形を作りやすくなる。出来ないわけではなかったが、千波が見ているという気恥ずかしさから「いやいや、お願いします」と遠慮した。
彼が電動ロクロの前に座った。用意してあった黄土色の粘土を取り出し、丸台の中心へ強く叩きつける。軸がブレないよう押し固めてから、足元のペダルを踏んだ。不格好な山の形をした粘土がロクロ台の上で回り始める。彼は陶器の深皿に入った水でたっぷりと手を濡らすと、その手を優しくあてがった。水気を帯びた粘土が艶めき、命を吹き込まれたようだった。
添わせた両手を下から引き上げていく。するとずんぐりむっくりしていた粘土が一気に伸び上がった。その光景を千波は初めて見たらしい。「すごーい!」と甲高い歓声を上げた。
粘土を引き上げたり押し倒したりするのを何度か繰り返してから、お兄さんはロクロを止めた。「じゃあ、座ってください」と席を立つ。促された私は木の丸椅子に腰かけた。ロクロ台を目の前にし、一層緊張感が高まる。
「何作りますか?」
「あーそうですね。じゃあ、タンブラーとか作りたいです」
「分かりました。タンブラーですと、かなり高さを出す必要があります。まずは粘土の中心に両手の親指を入れて空間を作っていきましょう」
「はい」
お兄さん、いや、師匠の言葉に大きく頷く。私も同じようにたっぷりと手へ水を付けてから粘土に触れた。ひんやりとした感触が心地良い。右足をペダルに置いた。つま先へ少しずつ体重をかけていく。師匠のアドバイス通り、粘土の中心を両親指の腹で押した。沖縄の土だからだろうか。思っていたより粘土が固い。
「手慣れていますね」
「はは、ありがとうございます」
粘土に沈んでいく親指を見つめたまま受け答えをする。どのくらいやっていたんですか、と師匠が尋ねた。
「そんなに長くはないですよ。半年くらいです」
「半年って結構やっていたと思いますよ」
「そうですかね? でも、もう丸一年やってないです。……就活を機に辞めてしまったので」
つま先を上げ、ロクロを止める。再び深皿へ手を入れた。乾くと滑りが悪くなってやりにくいのだ。水を付け様、ちらっと千波を見た。彼女はスマートフォンを片手に陶芸の様子を黙って眺めていた。私は製作に戻った。親指二本分空いた穴を少しずつ横へ広げていく。
就職活動を機にやめたと言ったが、それは事実でありながら建前でもある。三年間続けたサークル活動を引退すると、周囲のスイッチは余韻に浸る間もなく就職活動モードへ切り替わった。私も何かしなければとは思ったが、だからと言って身体が動くわけでもない。ただ、何かの職人になりたいという漠然とした思いはあったので、とりあえず自分のやりたいことを片っ端からやってみることにした。その中で最も印象深かったのが陶芸だ。新鮮だったのもあるが、初めてやった割に出来が良く、教室の先生からも筋が良いと褒められた。すっかり調子に乗った私は地元の陶芸教室に通うことにした。
陶芸教室は楽しかった。けれど、それ止まりだった。そこはプロになるための場所ではなく、あくまで陶芸を通したコミュニティだったからだ。レッスン生徒と自分とのズレを意識し、私はやめた。
「良い感じですね。もっと大きくしていきたいので、今度は親指以外の四本の指を使いましょう。両手で挟むようにして深さと高さを出します」
「はい」
もう一度水を付け、最初より二回りは膨らんだ粘土塊へ指を添えた。プレスする力を少しずつ加えていく。ドーナツくらい太さのあった縁は徐々に薄くなり、上へ伸びてきた。そこそこ力を入れているが、粘土を薄くしすぎると窯で焼いた時に穴が開いてしまうので、加減が難しい。
「就活を機にってことは、春から社会人ですか?」
「あ、そうです」
「へー。お仕事は何をされるんですか?」
「あ、えっと、WEBメディア関係です」
私の返答に師匠は分かっているような分かっていないような相槌を打ち、それ以上言及しなかった。大抵の人が同じような反応。けれど私も深掘りされたくないので良かった。というのも、以前知り合いのおじさんの会社で働くという話をしたら、「それ大丈夫なの?」と心配されたことがあったから。大きなお世話だと思った。私の進路があなたの人生に一体どんな関係があるというのだろう。少なくとも私は一年間模索しても、やりたい仕事は見つけられなかった。皆は天職と呼べる仕事に確実に出会えたというのだろうか。周囲が納得する企業名や企業ブランドで選んだという人は一人もいないのだろうか。
一旦止めてくださいと師匠に言われ、ペダルから足を離した。底から天に向かって末広がりになったそれは、タンブラーというより土器だ。けれど乾燥と焼成により水分が抜けていくので、このくらい大きくて良い。
「大分良い感じですね。もっとこうしたいとかありますか?」
「あー、そうですね。コロンとした形になるようもう少し飲み口をキュッとさせたいです」
私のリクエストを聞いて師匠がやり方を教える。それに倣って微調整を加えた。
「できました」
「お疲れ様でした」
師匠の言葉に私は肺に溜まっていた空気を長く吐き出した。出来たものロクロ台から糸で切り離し、渡された木板へ置く。手に着いた黄土色のドベを近場の水道水で洗い落とした。その後、色や模様をオプションで付けるかどうか訊かれたが、今のものが気に入ったのでこのままで良いと断った。
「じゃあ、二か月後くらいにお届けしますので」
「はい、宜しくお願いします」
深々と頭を下げる。師匠にもう一度お礼を言って、私は千波と工房を後にした。
坂を下っている途中、「結奈、見て」と千波がスマートフォンの画面を見せてきた。そこには真剣な表情でロクロを回す私が映っていた。
「いつの間に撮っていたのよ」
「あはは。だって結奈、すっごい楽しそうだったから」
そんな風に見えるか? 突っ込みたくなったが、千波が嬉しそうにしていたので、言葉を飲み込んだ。
やちむん通りに出ると、再び千波のマグカップ探しを始めた。意匠を凝らした様々なタンブラーを見るも、やはり自分で作ったものが一番良く思えた。
二か月後ということは、四月。働き始めて間もない頃だ。その時の私はどんなことを感じ、何を考えているだろう。少しはやりたい仕事だと思えているだろうか。未来のことは分からないが、仕事から帰ってくるなり手製のタンブラーにビールを注いで一杯やっている自分を想像して、頬がにやけた。
(完)

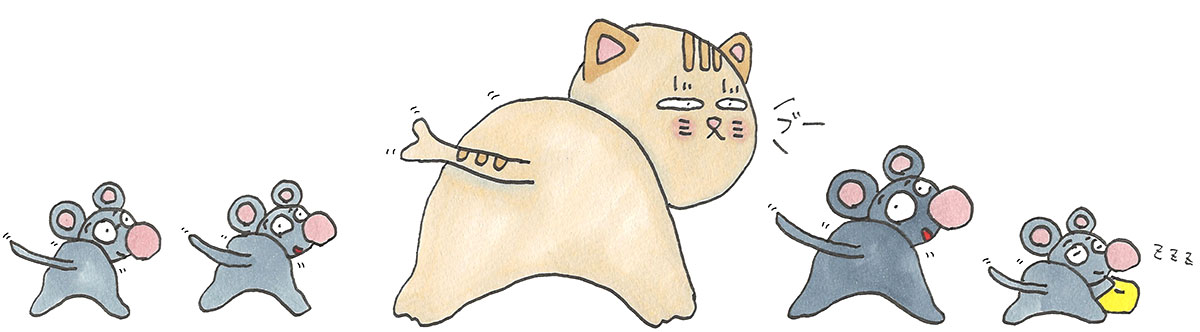







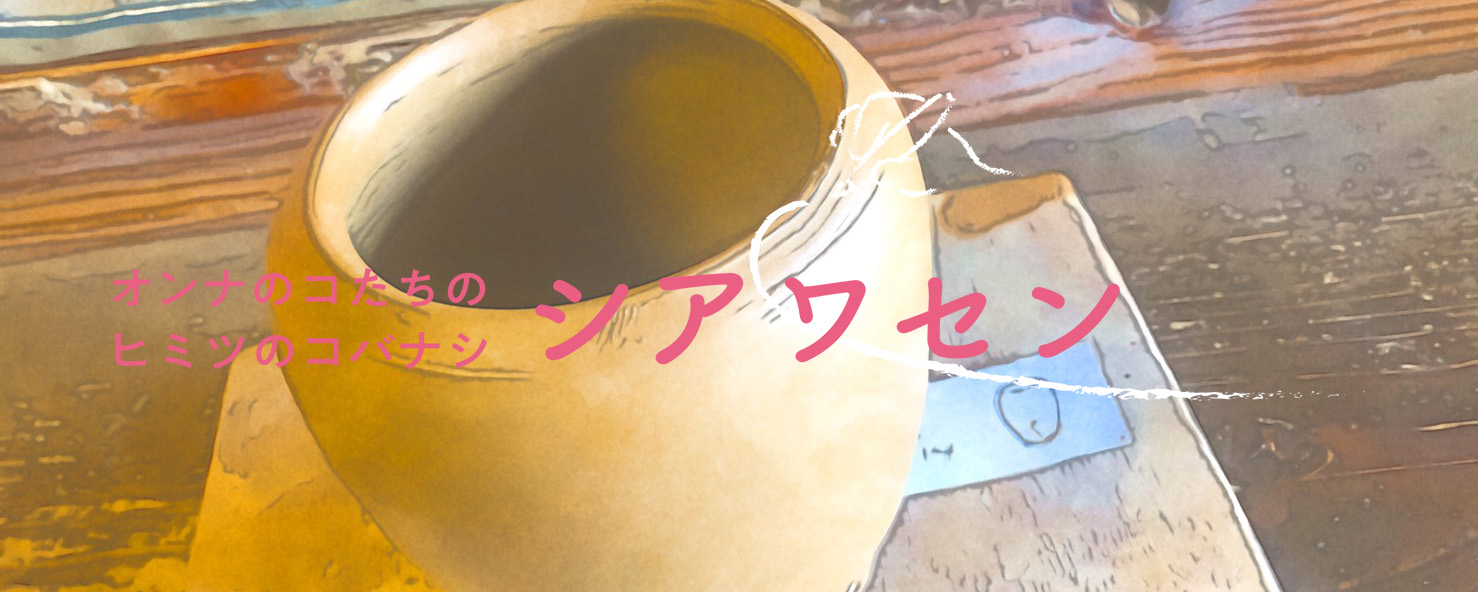

COMMENTS