「シロかクロか」
大人の世界はグレーだ。
齢二十四歳、社会人になってたった数ヶ月しか経っていない私でさえ、それをひしひしと感じる。学校生活が人生の全てだった高校生の頃は早く大人になりたいと切に願っていたはずなのに。大学生になってアルバイトを始め、酒の味を覚え、他人と肉体的な関係も人並みに嗜んだことで大人の階段を呆気なく登ってしまい、気づいた時にはもう社会という大海原へ放り出されていた。小さな船の一クルーとなった私は形も大きさも様々な他船を目の当たりにすることになる。やや他人事な言い回しをしているのは齢二十四歳の小娘であるだけにまだ実感があまりにも薄いからだ。クルーとはいえ、ライフジャケットを着せてもらっている状況は小さな子供と何ら変わりはない。ただ、そんな子供でも分かっていることがいくつかはある。大人の世界はグレーだということ、超えてはならない一線があるということ、それでも万が一超えてしまう場合は逃げ道をきちんと確保しておかなければならないということ。そして、それらは全て今の私に求められていることでもある。
ダウンライトが一定の間隔で埋め込まれたクリーム色の天井をぼんやりと眺めながら、自分の胸に右手を当てた。下半身へそろそろと降下していく。ごわごわしたパイル生地が手の甲に触れた。その一方で手のひらは素肌へ直に冷たさを与え、激しく二日酔いの頭を凍りつかせた。
天井から左隣へおそるおそる視線を移す。嫌な予想は的中。普段自分が使っているものの二倍はあるベッドで寝ているのは、自分だけではなかった。頭まですっぽりと被った埃っぽい布団が大きく盛り上がり、小さな上下運動を繰り返している。やっぱり、私はこの相手とラブホテルに入り……そういうことになってしまったようだ。
マズいな、これは。唇を舐めた。ロクに水を飲まずに寝たらしいことと室内の乾燥で口内が砂漠のようだったが、水を取りに冷蔵庫まで行く勇気はない。何せ記憶が全くないのだ。今隣で寝ている相手が誰なのかも分からない。そんな状況で私が起き上がったことに気づいて相手も起きてきたら、超気まずい。
まずは相手が誰なのかを確認する必要がある。そうしないと言い訳を考えることもできない。布団を捲るのは水と同じ理由で禁じ手だと思い、布団から出した片手を代わりに上へ伸ばした。こういうところは大抵、充電コードがヘッドボードかサイドボードのどちらかに備えつけてあるのだ。現代の必需品・スマホさえあれば、この状況を打開できる可能性は大いに高まる。それに今が何時なのかも知りたかった。今日が土曜日で仕事がないことは分かっているが、部屋に窓がなく外の光が差し込まないので具体的な時間が分からない。
私が思った通り、ヘッドボードに充電コードはあった。しかし、肝心のスマホが先端に刺さっていない。ここまで来ると、焦りを通り越して呆れてくる。一体、私のスマホはどこに行ってしまったんだ。まともに動くこともできないまま、私は脳内で飛ぶ前の記憶を遡り始めた。
昨夜の十九時過ぎ。私は新宿にあるチェーンの居酒屋で、大学時代に所属していた放送研究会の同期たちと酒を飲んでいた。メンバーは、城宮ユウヤ、玄田マコト、棒葉クルミ、木戸リョウスケ、そして私の五人。当時から仲が良かったのかと聞かれると返答に窮するが、卒業した今でも定期的に飲んだり遊んだりしていた。
会う度にするサークルの思い出話でひとしきり盛り上がり、場の空気が温まった後、「最近どうよ」と木戸が城宮に話題を振った。
木戸は某テレビ局に就職して二年目だ。現在はドラマのアシスタントをしているようだが、ゆくゆくはバラエティのプロデューサーを目指しているらしい。彼はサークルに入ったのが一緒の年なので同期という括りになるものの、学年自体は一つ上だ。そのため一浪している私と実年齢が同じである。
「まあまあかな。でも、楽しくやってるよ」
ハイボールの入ったグラスの縁から唇を離して城宮が答えた。歯並びの良い白い歯が覗く。淡白な顔立ちに似合わず二の腕のワイシャツがはち切れんばかりに張るほど鍛え抜かれた身体は、皆が思い描く理想の営業マンの姿だ。しかも、大手広告代理店勤務。いわゆるエリート街道というやつ。
「そうなんだ。営業って大変そうな感じあるけどなー」
「俺は人と話すの好きだし、そこは苦じゃないよ。ていうか、部署が営業なのは玄やんも同じじゃん?」
再びグラスへ口を付けながら、城宮が前の玄田へ目を向ける。
「ITって競合多そうな感じするけど。どう? ノルマとかきつい?」
「え? あ……えっと、どうなんだろう。自分的にはきついなあって感じるけど、同僚は全然クリアしてるし。単に俺が仕事できないだけかな。はは……」
紫色のカクテルに目線を落とし、力なく微笑んだ。そんな彼を見て城宮は目を細めた。黙ってグラスを傾ける。時折垣間見える彼のこういう仕草が私は苦手だった。そのことを改めて実感していると、私の隣に座っていたクルミが口を挟んだ。
「っていうか、そもそも玄やんって理系じゃん。エンジニア職なのに、どうして営業もやってんの?」
「えっと、なんか一年目はエンジニア職とか総合職とか関係なく、一通りの業務をルーティンでやることになってて。商材をより深く理解するため、みたい……」
消え入りそうな声で説明する。いくらルーティンとは言え、営業に彼が向いていないのは火を見るよりも明らかだった。彼は俗にいうセンスのあるタイプで、モノを生み出したり作ったりする方が得意なのだ。実際、放研ではその才覚をしっかりと発揮して活躍していた。
「まあ、働いてみないと何が自分に合うとか分からないからなー」
ハイボールを一気に飲み干し、メニューのタッチパネルで次の飲み物を選び始めた城宮がやや的外れな指摘をする。四年間も玄田の何を見てきたんだと咎めたくなったが、大手広告代理店マインドに染まってしまっている今の彼には何を言っても無駄だと悟った。周りとの温度差を感じ取ることができないまま、彼は大企業やベンチャーの良し悪しを我が物顔で語り始めた。
二十一時前、明日も朝早くから仕事があるらしい木戸が早々に抜けた。休日関係なく現場に出向かなければならない仕事は大変だなあと他人事な感想を抱いていると、「テレビ業界って超ストレス溜まりそうだよな」と城宮が四人になった場を回し始めた。ハイペースで飲んでいたせいか、かなり顔が赤らんでいる。
今、私の隣にいる可能性が高いのは順当に考えれば城宮だ。爽やかで清潔感のある雰囲気から学生時代はイケメンイケメンともてはやされ、本人もまんざらではなさそうだった。いや、むしろ調子にさえ乗っていた。一時期の彼は自分に寄ってくる女なら年齢関係なく手を出していたようだ。新宿のホテル街を庭にしているという噂を聞いたことも一度や二度ではない。就職してもその性欲はまだ鎮まっていないのだろうか。好み的にも私より酔うとキス魔になるクルミを落としにかかりそうだが、城宮であればこの場を乗り切るのはさほど難しくはなかった。彼は確かにプライドが高く他人を下に見る節がある。しかし、根は明るくてノリの良い男なのだ。「ごめん、昨日は酔っちゃって」と軽口でも叩けば、一夜の関係も笑いに変えてくれるだろう。
自分の中で答えが出た途端、緊張の糸が解けた。肺に溜まっていた空気を吐き出す。長かったが、これでやっと水を取りに行けそうだ。布団から這い出るため身を捩る。その時、私は驚愕の光景を目の当たりにした。そこには黒い手錠、同じ色のアイマスク、そして、ピンク色の細い縄……いわゆる大人の玩具が真っ赤な絨毯の敷かれた床の上に散乱していた。
思わず息を呑んだ。昨日のワンシーンが嫌でも思い出される。確か二十二時を過ぎたところだった。酒が回り、皆が口を滑らせるにはちょうど良い時間帯だ。
昔の話と仕事の話を終えた私たちの話題は、個人の話へと突入していた。個人の話で一番盛り上がるのは恋愛、中でもそれにまつわるゲス話である。それを最初に口にしたのは、意外にも玄田だった。どうやら学生時代から付き合っていた彼女と別れてしまったらしい。
「ええっ、あんなに仲良かったのに。どうして?」
驚きの声を上げながらも、クルミは身を乗り出した。酔いで潤んだ瞳がキラキラと輝いている。ようやく話題の中心権を得た玄田はへらへらと頭を掻いた。
「そのー、ちょっと言いづらいんだけど、やりすぎちゃったんだよね。あはは」
「やりすぎちゃった? まさか二股してたとか?」
「城宮じゃないんだからありえないでしょ」
「それは酷くねえ?」
私の手厳しい一言に城宮が突っ込む。皆がどっと笑った。
「二股とか浮気とかじゃないんだ。むしろ、その、夜の趣味の方で、ちょっと」
「夜の趣味?」
クルミが聞き返す。言ってなかったっけ、と玄田が少し首を傾げた。
「俺、SMプレイが趣味なんだよね」
唐突なカミングアウトに場が凍った。しかし、彼はそれを気にする風もなくぺらぺらと喋り始めた。一体、さっきまでの勢いのなさはどこに行ってしまったんだ。
「いや、最初は彼女も乗り気だったんだよ? お互いにハマっていたし。でも、そういうのって続けていくうちにヒートアップしていっちゃうだろ? それで、『もうあなたの趣味にはついて行けない』って言われて、別れたんだよ」
……マズいぞ、これは。
妙な体制のまま、私は唇をわなわなと震わせた。いくら記憶を掘り返しても思い出せそうになかった。けれどこの状況からして、それなりに愉しんでしまった事実は明白だ。言い逃れることなんて到底できない。
もし、もしも。隣で寝ているのが玄田だったとしたら。私はどんな顔をして彼に接すれば良いのだろう。「私たち、昨日どんなプレイしたっけ?」は流石にアウトだろう。その時はお互いに酔っていたから良いものの、今となっては気まずいだけだ。
私はおもむろに布団の中に戻っていった。どんなに脳みそをフル回転させたところでこの場を乗り切る打開策が浮かぶとは思えない。それなら取れる行動は一つに絞られる。何もせず悪い夢だったともうひと眠りすること。つまりは現実逃避である。
先ほどと同じように仰向けになる。自分の死期を悟ってゆっくりと最期を迎える老婆のような気持ちになりながら、私は少しずつ瞼を落としていった。光が徐々に細くなり、辺りが完全に真っ暗になる――寸前、相手がこちらに寝返りを打ってきた。足先に相手の脛が触れ、思わずぎょっとなる。遂にタイムリミットのようだ。きつく目を閉じた。心臓が早鐘を打ち始める。そのリズムに合わせるように隣が大きく蠢いた。
布団とシーツの衣擦れを耳にする中、ちょっとだけ冷静な自分もいた。違和感、という言葉の方が適切だろう。その要因は当たった脛が妙にきめ細やかでしっとりとした肌質だったことだ。
玄田は割と剛毛だ。夏場になると決まって半ズボンを履く彼の生脚に何度げんなりさせられたことか。それに比べれば城宮は毛が薄い。玄田の激白にあんなにドン引いていたのに。実際には城宮もそういう性癖の持ち主だったのだろうか。
城宮か、玄田か……シロかクロか、どっちだ。
布団が一気に剥ぎ取られた。こめかみの辺りに一層光を感じる。
おそるおそる目を開けた。視界に入ったのは、艶のある長い髪の毛。そして化粧っ気のない青白い丸顔。
「おはよう~」
私を見て、クルミが大きく伸びをした。羽織っただけのローブの隙間から豊満な乳房が覗いている。彼女も私と同様、下着を付けていなかった。
突っ込みたいこと、聞きたいことはたくさんあった。しかし予想外の出来事に頭が真っ白になってしまった私は、考えるよりも先に口を動かしていた。
「お前かよ」
(完)

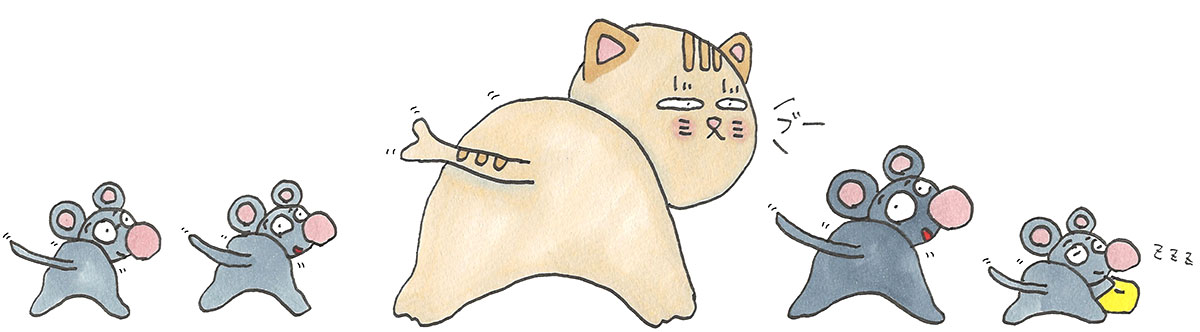









COMMENTS